AIの進化と雇用・労使関係
技術の導入と労使関係のかかわり新技術の導入は受け入れつつも
雇用の場はしっかり求めるべき

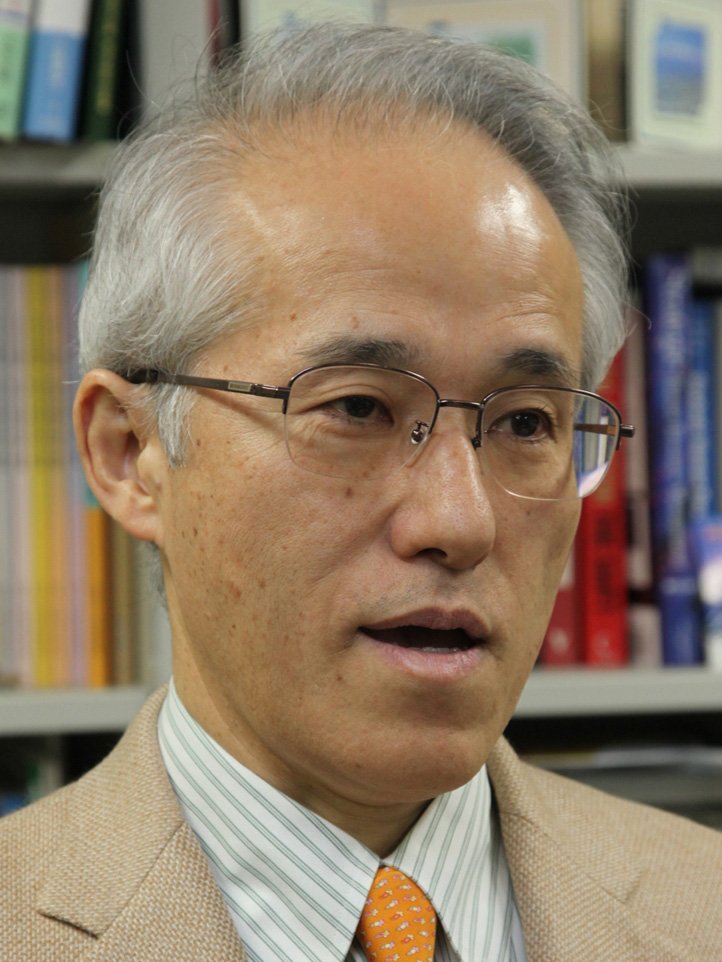
研修機構(JILPT) 理事長
新技術とメンバーシップ型
日本の労使関係は、メンバーシップ型と呼ばれる関係の中で、ある仕事がなくなっても、その仕事をしていた人を別の業務や場所に移して、雇用を維持することを大事にしてきました。これは、新しい技術が導入され、機械が業務を代替しても基本的には同じことで、日本の労使は雇用維持に努めてきました。
そのことを象徴的に表すのが、1980年代のME化(マイクロエレクトロニクス)への対応です。当時、小型化された電子機器を搭載した機械による自動化が進む中で、極端に言えばそれまで10人で行っていた仕事を2人でできるようになりました。その結果、8人が解雇されて、失業者が増えたかというと、そうはならず、余剰となった8人を別の仕事に移すことで雇用を維持しました。当時の変化は非常に大きなものでしたが、それを乗り越えてきたことを踏まえれば、今回のAIの進化でも類似した動きが起きるのではないかと考えています。
連合総研の調査では、日本の労働組合は、雇用に関する部分については積極的に発言するものの、新しい技術の導入に関しては積極的にかかわってきませんでした。つまり、日本の労働組合は、雇用に影響しなければ、新技術の導入を受け入れてきたといえます。
代替の各国比較
一方、ジョブ型の労使関係が中心である欧米は、日本と事情が異なります。ジョブ型の世界では、機械によってその業務が代替されると、その業務をしていた人の雇用も失われるのが基本です。そのため、技術革新に対する抵抗は比較的強かったといえます。
アメリカではそうした傾向が特に強くありました。アメリカの経営者は、労働組合の強い北部地域ではなく、労働組合の組織率が低く、抵抗が弱い南部の地域に新しい工場をつくり、そこに新技術を導入していきました。アメリカで、IT企業が成長した背景にも同国の労使関係が影響していたと言えます。労働組合の結成を避けるために情報化投資を進めてきました。
ドイツなどの大陸系ヨーロッパの労使関係は、ジョブ型といってもアメリカとは少し異なり、労働組合や従業員代表制度において新技術の導入について話し合いができる土壌がありました。
現在、JILPTでは、OECD8カ国と、AIの職場への導入に関する共同研究を行っています。各国の製造業と金融業の企業を4社ずつ取り上げ、AI導入後の働き方の変化を調べています。
一次的な比較結果によると、業務のすべてがAIに置き換えられる事象は、どの国でも起きていませんでした。業務の一部がAIに置き換わっても、すべてをAIに任せると責任の所在が不明確になるため、どの国でも人間のかかわりを残していました。このようにAIが進化したからといって、すべての仕事がAIに置き換わるわけではありません。ただし、この調査は、生成AIが登場する前の調査であることに留意が必要です。
日本型労使関係の課題
生成AIのような新しい技術の導入に当たっても、これまでの日本的労使関係を生かすことが有効だと思います。例えば、鉄鋼の労働組合は、新技術の導入に反対してきませんでしたが、その代わりに、新しい機械が代替する業務を担当していた人の雇用については、会社側に繰り返し対応を求めてきました。こうした方法は、生成AIのような新しい技術の導入に当たっても通用するはずです。新技術の導入によって企業の力が高まるのなら反対はしないけれど、その結果、雇用の余剰が生じるならば、働く場の確保を求めていく。そこはこれからもしっかり追求していくべきだと思います。
ただし、次のことに注意が必要です。1980年代当時は、ME化でコストが低下し、生産量が増えても、国内消費や海外への輸出が旺盛だったため、生産性が向上して生じた雇用の余剰に対応できました。しかし現在は国内消費が当時に比べて減退しているので、AIの生産性の向上で生じた雇用の余剰をまかない切れるかという問題は起こり得ます。だからこそ、労働組合が雇用の場の確保をしっかり求めていく必要があります。
日本の労使関係は、第二次世界大戦後、1960年代半ばくらいまで労使の対立関係が基本でした。労働組合は、経営側の言うことにとりあえず反対していました。60年代終わり頃から、経営側との話し合いを重視するリーダーが登場し、対立すべきところは対立しても、会社との協議によって労働者の利益を実現していこうという流れが生まれました。対立と協調の時代です。
それが1980年代以降、労使ともに世代交代が進み、労働組合のリーダーも大卒層が中心となり、経営者も経済合理性をより強く追求するようになり、バブル崩壊が起きました。
日本の労使関係はその後、労使がともに「守り」に入ります。経営者は企業を何とか存続させようとし、労働組合も会社と似た思考をするようになりました。バブル崩壊という経済不況に対し、緊急避難的に取る行動としては仕方なかったかもしれません。しかし、その考え方は、2000年代以降、日本経済がバブル崩壊から立ち直っても続きました。現在の労働組合は、あまりにも経営側に近づき過ぎています。労働組合は、会社ともっと議論をすべきです。行き過ぎた労使協調を見直し、「対立と協調」の関係を取り戻すべきだと思います。
変化に対応する力
新技術のような時代の変化に対応するためには、労働組合が組合員をサポートすることも大切です。日本のビジネスパーソンは、国際的に見ても、自分自身を磨くために勉強する時間がとても少なくなっています。メンバーシップ型の労使関係の中で、企業の用意する仕事をこなしていれば大丈夫という安心感がありましたが、そうした土台が危うくなっています。変化が起きたときに対応できる人材になっておく必要があります。
ここに労働組合の役割があります。組合員が時代の変化に対応できる力を身に付けるためのサポートです。例えば、製造業のある組合の支部では、その分野で仕事をする上で知っておいた方が良い海外の論文を労働組合主催の勉強会で学習するということをしていました。好評で参加率は高かったそうです。同じことを会社の命令でやれば、業務命令になってしまいます。労働組合が自主的に組合員の学習をサポートすることで、変化を乗り切る力を提供することができます。
政府の役割
生成AIの導入に当たって政府に期待する役割の一つは、著作権の保護です。ある人が時間と労力をかけてつくったものには価値があり、それを利用するなら、正当な対価を支払わなければいけません。誰かがつくった著作物を勝手に使ってはいけない。そういうルールの土台をつくるのは政府の役割だと思います。
人が生み出したモノやサービスには、正当な価格があります。しかし、日本の場合、「サービスは無料」という考え方が根深くあります。「送料無料」という表示は、その象徴です。実際には、そのモノを運ぶために費用が生じています。
運輸業界では1990年代に規制緩和が行われた結果、参入する業者が増えすぎて価格競争が起こり、ドライバーの賃金が低下した結果、成り手不足が顕在化し、現在の物流危機につながっています。正当な価格を下回るような競争のあり方には、消費者としても疑問を持たなければいけません。モノやサービスが正当な価格を維持できるように、適切に規制していくのも政府の役割だと思います。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

