徹夜神話を疑おう
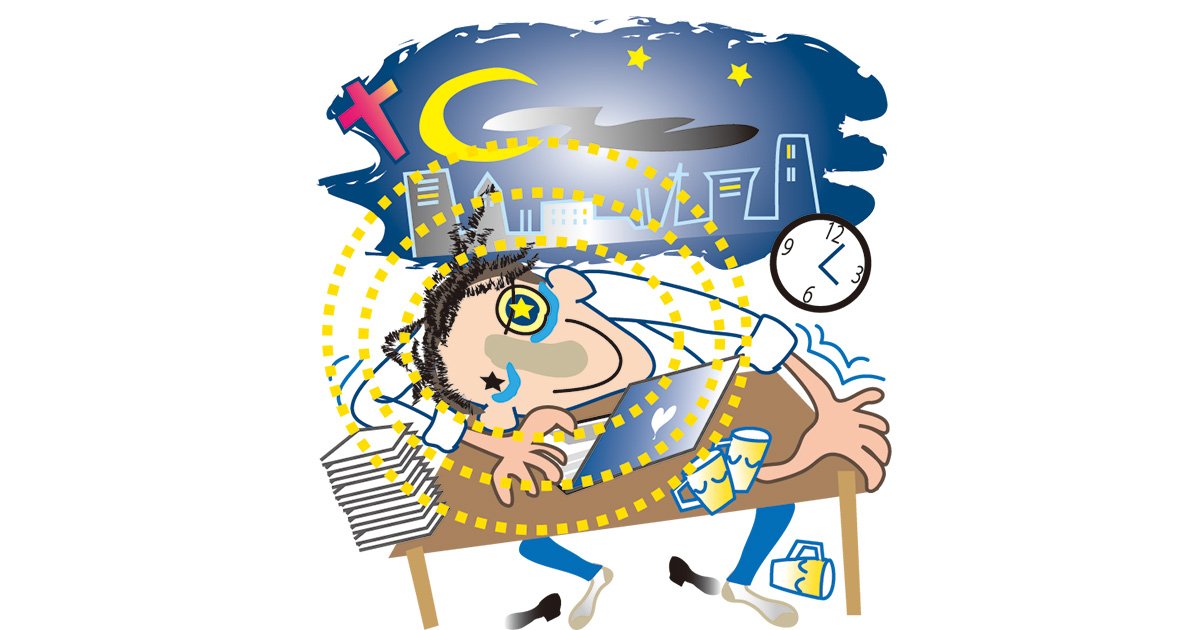
そういえば、40代になってから仕事で徹夜をしなくなった。体力的にもできなくなった。プライベートでも年に1度、オールナイトの音楽イベントに参加するときだけだ。以前は、後期高齢者が朝までほえる番組を見ていたが、「なぜ、昼間やらないのか」と疑問に思い、見るのをやめた。寝不足は教育者、評論家の仕事に悪影響を与える。父親としてもよくない。夜と休日は基本、働かない。これで、困らない。
20代の頃、一生分の徹夜をした。もう、安らかに眠らせてほしい。当時の勤務先は漆黒のブラック企業だった。「不夜城」という城が本当に存在するとは。かなりの城マニアでも、不夜城を訪問したことのある人は、まずいないだろう。ただ、城マニアがうらやましがるイメージがまるで湧かない。9 to 5の日々だった。定時あがりのお気楽な日々ではない。毎日終電で、週に何度かは朝まで働き、山手線で仮眠をとり、サウナで汗を流して出勤した。21時台に終わる日は早く終わったと感じ、思わず同僚と飲みに行き、結局、終電になった。週末は休日出勤だった。
もっとも、徹夜に高揚感があったこともまた事実だ。寝静まった夜に、世の中を震撼させるような、すごい企画を考えているかのような気分になった。みんな深夜残業をしているので、夜に相談、雑談がそのまま会議に発展したりもした。どうせみんな、タクシー帰りだろうということで、深夜や早朝に飲み会が始まるのもよくあることで、そこでは仕事関連の熱い話になった。あたかも、ビジネスに関する「戦闘力」が上がったかのような感覚にもなった。残業代もたっぷりついた。ほぼ、飲み代とタクシー代で消えてしまったが。
とはいえ、徹夜は長時間労働そのものである。間違いなく、健康に悪影響を及ぼす。
この徹夜はときに美談化される。「やらされる残業ではなく、自ら望む残業なら良いのでは?」という意見の方もいることだろう。スピードがモノを言う時代でもある。グローバル競争を勝ち抜くためには、徹夜も必要だという言説まで存在する。若いうちは無理もきくし、家庭の事情なども少ないので、この時期に経験を積むべきという意見もある。
最近では「ゆるブラック企業」なる言葉も話題となっている。残業も少なく、ハラスメントも皆無なのだが、やりがいも成長感もない企業というものだ。残業、ハラスメントを礼賛しているわけではないことに注意したいのだが、まるで若者がきつい職場を求めているかのような誤解を呼んでいる。
しかし、この残業は素晴らしいことなのだろうか。労働強化につながる状態にすり替えられていないか。結局、得するのは経営者ではないか。AIなどが発達する中、残業を減らして職場が回る仕組みを考えた方が有益ではないか。徹夜は自己満足を装った、経営側の論理であり、百害あって一利なしなのである。このような論理の下で、労働強化が起きてはたまったものではない。
制約は人と組織を強くする。残業しない前提で会社と社会が回るように模索するべきではないか。大義名分を悪用した徹夜神話、礼賛論こそ時代遅れなのである。徹夜なしの会社と社会を考えよう。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

