【第7編】労働組合〜ジェンダーギャップ最劣悪国でどうしますか〜クミジョ・クミダンのパートナーシップ
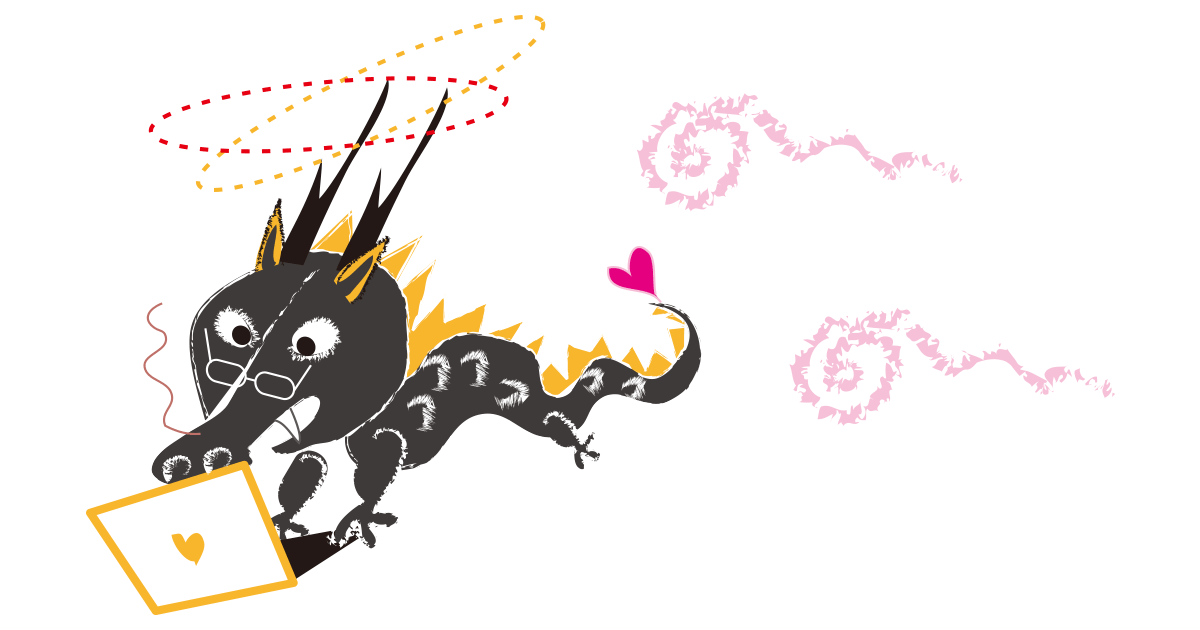
男女共同参画やジェンダー平等を職場や社会のこととして取り組む労組が、実は自らの組織内部でできていない愚を避けたいところです。そうしないと、誰ひとり取り残さないどころか、みんな一目散に逃げて行きます。
その争点を二次元的権力で吹き飛ばさず、逃げずにやり抜くぞ、という気概が持てる労組なら、クミジョとクミダンのパートナーシップを築くスタートラインに立てます。そこからどうするか。クミジョとクミダンにアイデアを聞いてみたいところです。
まず、本気で取り組む時間を捻出するために活動の効率化が必要です。勇気を持ってビルド・アンド・ビルドはやめ、伝統や慣行を棚卸ししてスクラップすること。つくり出した時間や予算をつぎ込みます。何に? 三つだけ述べます。
第1に、学習会やセミナーなど研修体系を全部見直し、労組の一員としての知識やノウハウだけでなく、次世代も見据えた国民として、論点ずらしをせず、男女を凝視する学習を始めましょう。
第2に、お互いを知るための調査や意見や情報の収集を重ね、パートナーシップの現状を「見える化」する。不都合なことが出てきても、もみ消したり、書き換えたりせずに、当事者に寄り添う仕組みがほしい。
第3に、アリバイづくりの先送り計画とありきたりな弥縫策はやめ、順番を逆にして、パートナーシップが実現した後に何をどうしたいのかを先に男女で協議します。合意して全員が心に刻むことです。
スケジュールと期限を決めて実行するのは不可欠です。全体像と本気度が見えていれば、それならやってみます、という仲間を集めやすくなります。その瞬間からクミジョは増えます。
正真正銘のパートナーシップづくりを組織内部で完遂するのは難しいものです。研修や調査の実施、相談助言、現状と課題の評価、定期的な労働界への提言などができて、やる気のある労組と伴走する第三者団体が必要です。なければ、つくらねばなりません。
主著に『女性活躍不可能社会ニッポン 原点は丸子警報器主婦パート事件にあった!』(旬報社)、「万博の労働者が危ない—エキスポ1970で何が起きたのか」『労働法律旬報』(2024.10.25)など。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

