戦後80年を考える
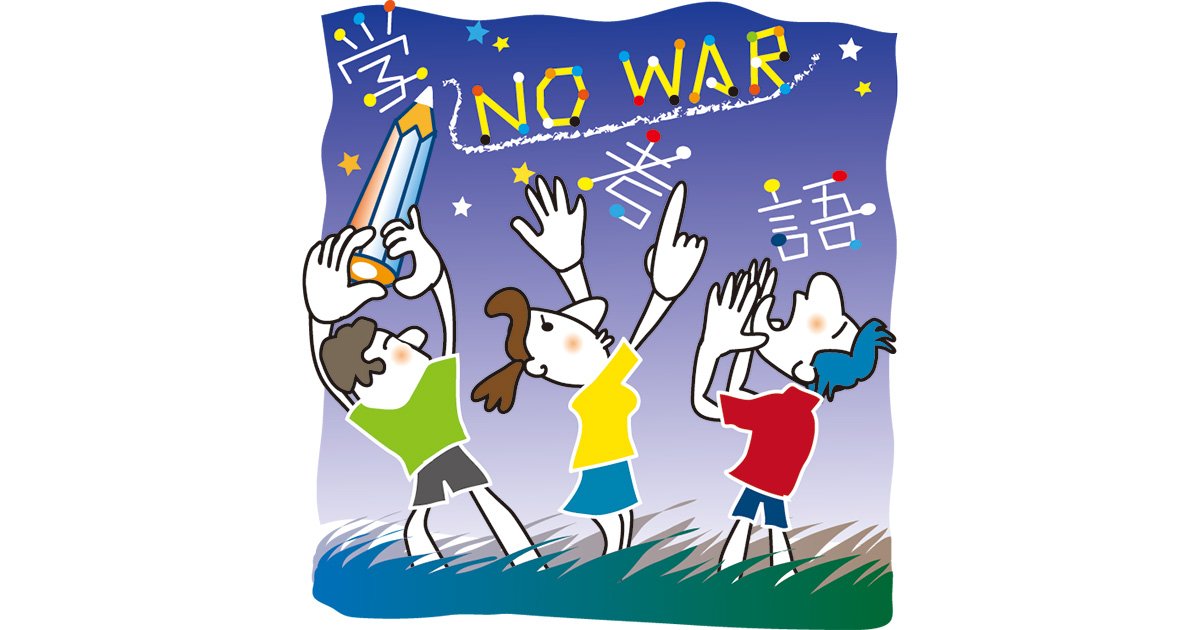
戦争について考える。徒然なるままに書く。「大磯のおじさん」のことを思い出した。神奈川県の大磯に住んでいた。大酒飲みで、酔うとたちが悪く、正直苦手だった。早く亡くなった。その後、おじさんの人生について知る。幼少期は裕福な家庭だったが、やがて家業は傾いた。戦場に行き、終戦後はシベリア抑留だった。おじさんのアルコール依存の理由を想像した。ほかにも満州や樺太からの帰還など、家族・親族から悲惨な話を直接、聞くことができたのは、今、思うと貴重な体験だった。
戦争については、コンテンツを通じて知ることもできる。小2のクリスマスに、真っ赤なサンタクロースが戦争や原爆のもたらした悲劇を描いた『はだしのゲン』を私の枕元に置いてくれた。小学生には、しかも2年生にはインパクトが強すぎる作品だったが、戦争と平和に目覚めた。特に第二次世界大戦での原爆投下、特攻隊、沖縄戦などに関して「なぜ、こんなことが起こってしまったのか」と衝撃を受けた。
30年前、大学3年の頃、初めてのアメリカ旅行の機内で読んだのが、今年、鬼籍に入った経営学者・野中郁次郎らによる『失敗の本質』である。日本軍の戦略と組織に注目し、なぜ日本は戦争に負けたのかを研究したものだ。ノモンハン事件、ミッドウェー作戦、ガダルカナル作戦、インパール作戦、レイテ沖海戦、沖縄戦などを取り上げ、現状認識の甘さ、曖昧な戦略、組織の硬直化などの問題を指摘したものだ。第二次世界大戦で、日本軍の死者の多くは、戦死ではなく病死、餓死だった。怒りが込み上げてくる。
半藤一利によるノンフィクション小説をもとにした映画『日本のいちばん長い日』も忘れられない作品だ。ポツダム宣言受諾を巡る天皇や軍部のドラマを描いたものである。歴史学者・加藤陽子の『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』と合わせて読みたい。「なし崩し的」に戦争に進む人間の姿が描かれる。
山崎豊子の作品にも戦争を描いたものが多い。本木雅弘主演でドラマ化された、沖縄密約の真相に迫るジャーナリストを描いた『運命の人』や何度かドラマ化された『二つの祖国』もそうだ。国と向き合う個人が描かれる。特に前者における、沖縄の描写は強烈である。沖縄戦のむごたらしさ、そして今も基地問題、米兵の暴行事件などと向き合う様子が描かれる。戦争はすべてを壊していく。
戦争を起こさないためにどうするかを考えたい。勇気をもって、高齢の家族・親族に戦争のことを聞いてみよう。戦争のことを忘れてはいけないし、二度と悲劇を繰り返さないためにも、変化に敏感にならなくてはならないのだ。
さらには戦争から学びたい。自社の職場で、暴走状態などが起きていないだろうか。それに対して声を上げること、これも戦争を忘れず、語り継ぐという行為である。
戦争のときは平和を祈り、平和のときには戦争の準備をする。悲しいことに、これが人類の歴史である。戦後80年の今、戦争のことを忘れてはいけない。学ぶこと、考えること、語ること、これが大切だ。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

