企業組織再編と労働組合
働く人の視点からすべきこと組織再編に対する連合の考え方
「労働者保護ルールの強化が必要」
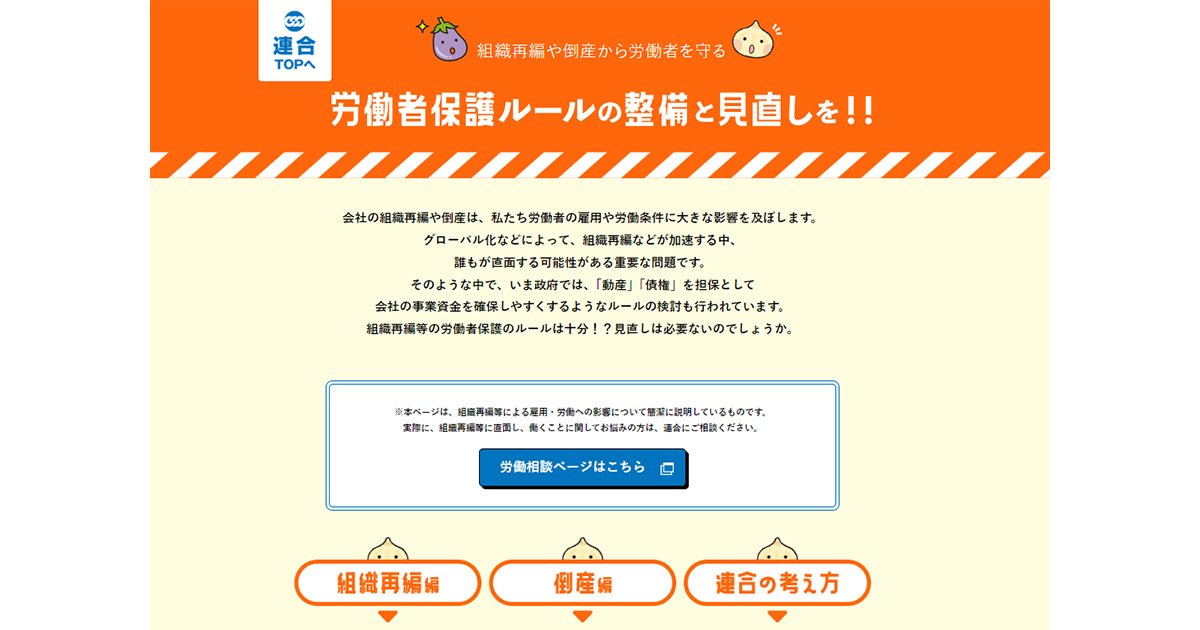

──組織再編にかかわる労働者保護ルールの現状を教えてください。
企業の倒産やM&Aの増加で組織再編が活発化する中、起業や組織再編を容易にする法改正が進んでいます。
一方、労働者保護ルールの強化は置き去りになっています。2000年に会社分割に伴う労働契約承継法が制定され、その後2016年に施行規則と指針が改正されましたが、法改正はなされていません。また、事業譲渡に関する指針も2016年に策定されましたが、今でも法整備には至っていません。このように組織再編に伴う労働者保護ルールの整備・強化は進んでいないのが現状です。
こうした中、連合は2009年に「事業組織の再編における労働者保護に関する法律案要綱」を作成し、組織再編時における労働者保護の法整備の必要性を訴えるなど、働きかけを強めてきました。
──労働者は現在どのような不利益を被っているのでしょうか。
組織再編は、経営の効率化や事業再生を目的に行われることが多い一方で、労働者が深刻な影響を受けることが少なくありません。再編に伴って解雇される場合もあれば、転居を伴う配置転換を求められ、その後、実質的に退職を余儀なくされるケースもあります。また、雇用が維持されても労働条件の引き下げを求められた場合、「生活のために受け入れざるを得ない」のが実態で、労働者が泣き寝入りするケースも少なくありません。
また、会社分割では不採算事業を切り離し、その部門を将来的に縮小・廃止する、いわゆる「泥船分割」があります。この場合、不採算部門と一緒に承継された労働者の解雇リスクが高まります。
会社分割には労働契約承継法が適用され、分割時の雇用や労働条件は一定程度保障されるものの、事業譲渡にはそのようなルールがありません。そのため、転籍時に労働条件の不利益変更を迫られることがあります。労働者としては転籍しなければ雇用を失うことになるので受け入れざるを得ないケースが多く存在します。
もう一つ大きな問題は、労働組合が譲渡先の企業と交渉できないことです。分割元・譲渡元との団体交渉は、厚労省の指針でも求められているのですが、分割先・譲渡先との団体交渉や協議に関するルールは現状では存在しません。実際、組織再編の場面では一般的に買い手側の立場が強く、買い手側の企業との交渉が重要になるのですが、それができない状態です。そうした団体交渉の相手方の使用者性の課題もあり、大きな問題になっています。
──現状の保護ルールの問題点は?
会社分割に適用される労働契約承継法は、労働者が現在就いている仕事を守る仕組みです。そのため分割される事業に主として従事している労働者の労働契約は、分割先の会社に自動的に承継されます。ただし、その一方で、労働者が「分割先には移りたくない」「元の会社に残りたい」と考えた場合でも、異議申し立てをすることができません。
会社分割には労働契約承継法が適用されるものの、事業譲渡にはこのような法律がありません。そのため労働契約承継法にある労働組合との協議や通知といったルールも存在しません。
事業譲渡の場合、どの労働者の雇用を引き継ぐのかも会社間の個別契約に基づいて決められます。そのため、「この人はOK」「この人はだめ」という選別も可能です。転籍には労働者の個別同意が必要になりますが、雇用を失うリスクを踏まえれば労働者がそれを拒否することは難しいのが実態です。
さらに会社分割でも事業譲渡でも、分割先・譲渡先の会社の関与が求められていないため、協議などの実効性が確保されないという課題もあります。
──連合としてはどのような見直しを求めていますか?
基本的な考え方としては、会社分割および事業譲渡のいずれの場合でも、分割元・譲渡元の事業に従事する労働者の労働契約は、すべて分割先や譲渡先に承継されることを求めています。その上で、移転元・移転先どちらの会社に対しても労働組合などとの協議や情報提供を義務付けることを求めています。
労働者個人は「ノー」ということが難しいため、労働組合を通じて集団的に交渉することが労働者の不安の解消や納得感の向上につながると考えています。
具体的には労働契約承継法の指針等の内容を充実させ、法律として格上げすることや、事業譲渡における労働者保護ルールの法制化を求めています。
──見直しの現状はどうでしょうか?
今年3月から厚生労働省で「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」が設置され、事業譲渡などの指針の見直しや組織再編全般における労働者保護ルールに関する議論が始まっています。労働者側は今述べたように労働者保護ルールの強化を求めていますが、使用者側は指針の法律への格上げには慎重です。
──連合としてはどのような取り組みを展開していきますか?
連合はこの間、学習会や集会を開催するとともに、『労働組合のための組織再編・倒産対策ハンドブック』を作成し、意識醸成や世論喚起に努めてきました。また国や政党への要請行動も行い、労働者保護ルールの強化を継続して訴えてきました。ただ、この問題は、実際に自分の身に起きてみないとイメージが湧きづらいというのが現実です。関心を持ってもらうために定期的に訴えることが大切だと考えています。
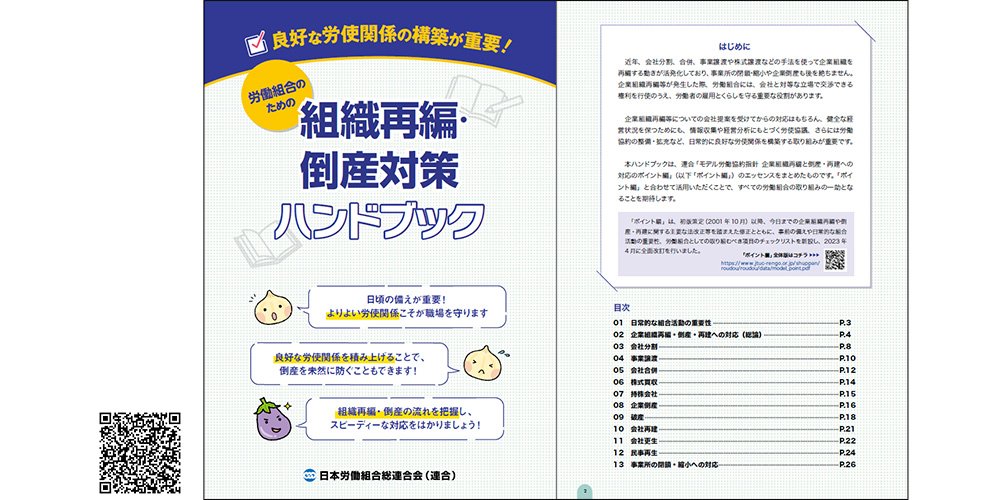
──労働組合にできる対策とは?
会社と経営に関する議論をきちんとできる労使関係を日頃からつくっておくことが非常に重要です。
労働組合の強みは、現場の声を聞けることです。その中には将来的なトラブルの兆しも含まれます。そうした声を受け止め、会社に対して「これはどうなっているのか」と確認し合える関係が非常に重要です。そうした関係を築いておけば、組織再編時にも必ず生きてきます。
組織再編の兆しをいち早く察知できるのは、関連部門にいる組合員の気づきともいわれています。会社とのコミュニケーションを図る一方で、組合員とコミュニケーションを図り、情報を共有することも大切だと思います。
また、組織再編にかかわる正しい知識を持っておくといざというときの備えになります。上場企業でもないのに、「インサイダー情報だから言えない」と情報提供を拒む会社もあります。こうした場合でも労働組合が正しい知識を持っていれば、冷静に対応できます。
連合が作成した、『労働組合のための組織再編・倒産対策ハンドブック』をぜひ活用してほしいですね。
──今後に向けて一言。
企業を支えているのは、一人ひとりの労働者です。組織再編でも、働く人の納得感を高めれば、紛争のリスクが減り、働く人の意欲が高まり、その後の事業運営もスムーズに進むはずです。私たちは、組織再編時にも働く人を大切にすることが一番重要だと考えています。これからもそのことを訴えていきます。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

