72年目の戦後責任
過去と向き合い、未来をつくる「レスポンシビリティ」としての戦後責任論
歴史を知り、応答することから始まる

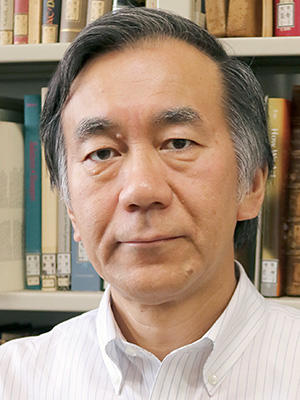
何が戦後責任なのか
戦後50年の際、私はレスポンシビリティ(responsibility)という言葉を使って『戦後責任論』を展開しました。レスポンシビリティとは責任の英訳です。その元となるレスポンス(response)という言葉は応答を意味する言葉です。レスポンシブル(responsible)とは責任があるという意味ですが、その原義は応答できるということです。そこから私はレスポンシビリティを応答可能性という意味で捉え、責任とは他者の呼びかけに対して、応えることだと訴えました。
東西冷戦が終結した当時は、東アジアでも軍事政権から民主化へと移行し、新たな政治情勢が生まれていました。その中から、日本がかつて周辺諸国に対して行った侵略や戦争犯罪について、被害者が次々と声を上げ始めたのです。戦後補償を求める裁判は100件近く提訴されました。こうした事態に戦後生まれを中心とした世代から「私たちには責任がない」という発言が数多く上がりました。
これに対して私は応答可能性としての戦後責任を主張しました。同じ時代を生きる隣人から私たちに訴えが投げかけられている。その呼びかけに対して、私たちは日本の主権者として「知らない」と無視することができるでしょうか、と。
呼びかけと応答
「呼びかけ」と「応答」は、人間の最も基本的なコミュニケーションです。例えば、路上で倒れて助けを求めている人がいたとしたら、私たちは助けようとします。友人からあいさつされたら、あいさつを返します。その関係は、母親と赤ちゃんから始まっています。このように人間の基本的なコミュニケーションである呼びかけと応答という観点で戦後責任を捉えたとき、私たちは隣人からの訴えを無視できるだろうかということです。
もちろん、助けを求められても無視して通り過ぎ、あいさつされても応えないという選択肢はあります。ですが、そうした態度をとれば、相手との関係は悪化します。周辺国との関係では、もともと日本に対して不信感を抱いていたものが、呼びかけに応答しないことで不信感はさらに増大します。果たして、それでよいのかというのが私の訴えでした。
自分が生まれる前に起きたことについて、謝罪を求められても困るという感覚は理解できます。それでも他者からの呼びかけがある限り、私たちはその呼びかけにどのように応答するかを考えなければなりません。そのためには、まず歴史を知る必要があります。どのように応答するかは、その歴史を知った上でそれぞれが判断を下せばよいのです。このことを踏まえても私は日本が国として謝罪や補償をすべきだと考えています。したがって日本の有権者として政府にそれらの実行を求めていくべきだと訴えました。
責任を認めない勢力の台頭
戦後50年から20年以上経過しても戦後責任は大問題であり続けています。問題が解消しないのは、やはり被害を受けた人々からの納得を得られていないことが本質だと思います。この間、日本政府は河野談話や村山談話を発表し、一定の責任を認めてきました。昨年末には慰安婦問題に関する日韓合意もありました。ですが、問題が解消されたとは言い切れません。というのも、やはり被害者の方々からの納得が得られていないからです。世論調査でも昨年末の日韓合意について、その内容を評価するとした人は、韓国で約20%、日本でも50%未満しかいませんでした。お互いが不満とする内容は異なると思いますが、このように双方の意思はかみ合っていません。
それに加えて、河野談話などで政府が一定の対応をしても、それに公然と反対する重要閣僚や与党幹部が次々と現れてくることも、問題の解決を遠ざけています。こうした態度をとり続ければ、相手は不信を抱くでしょう。
日本の戦後責任を認めようとしない政治グループは90年代に台頭しました。安倍晋三首相はそうした若手グループの中心メンバーでした。90年代後半になると、いわゆる「自由主義史観」がメディアで取り上げられるようになり、影響力を発揮しはじめます。そして、その流れは歴史修正主義的な政治家グループの台頭につながり、05年の第一次安倍内閣の誕生へと連なっていきます。一度、右傾化した世論の傾向は容易に元に戻らず、民主党政権の挫折や中国脅威論を背景に一挙に政治の中心に躍り出たのです。
国際的に通用しない歴史認識
歴史修正主義的な言説が雑誌やメディアにもあふれている状況で、歴史認識を変えていくのは容易ではありません。
とはいえ、この状況のままでいいわけではありません。まず一つ目に、日本の戦後責任を認めない歴史観は、国際的に通用しません。安倍首相が13年に靖国神社に参拝した際に日本を批判したのは中国や韓国だけではありませんでした。台湾やアメリカ、EU諸国も懸念を示しました。歴史修正主義者は、中国や韓国だけが日本を批判し、日本は他国からは信頼されていると主張しますが、誤った歴史認識を主張すれば世界から批判されるのです。慰安婦問題もこれと同じです。強制連行はなかった、業者の責任であると主張しても、通用しないのです。それどころか、そうした対応はかえって国際的な不信を招いています。
私は歴史認識問題に関して日本は「ガラパゴス化」していると考えています。インターネット上には日本の戦後責任を認めない言説があふれているかもしれません。しかし、国際的な視点ではそれは通用しないのです。国際的な視点をつうじてそのことに気づくことができれば、私たちはあらためて過去を真剣に学ぼうとするかもしれません。
二つ目に、中国や韓国などのアジアの国々は私たちにとって永遠の隣人であるということです。日米関係だけが安定していれば、日本の安全保障が担保されるわけではありません。日本が東アジア地域で持続可能な安全保障秩序を求めていくのであれば、隣国との安定した外交関係が欠かせません。その大前提となるのが歴史認識なのです。
歴史を知るという戦後責任
歴史認識が問われるのは国だけではありません。私たち一人ひとりも歴史認識を問われています。私の個人的な経験からも、日本がアジアの国々にどのような被害を与えたのかを知らないことは、相手に対して強い不信感を与えます。
例えば、南京大虐殺のことを知らない(むしろでっち上げだと思っている人々も多い)、重慶爆撃や平頂山事件のことを知らない。韓国植民地化のプロセスや日本がオーストラリアを攻撃したことを知らない─。しかし相手はそれらのことをよく知っています。オーストラリアの戦争記念館には日本との戦争の歴史が展示されていて、小学校の児童たちなどが学習しています。
けれども私たちはそうした歴史を知らない。戦争の歴史は、被害を受けた側の方がよく覚えています。被害を与えた側が加害の歴史を知らないのでは、相手が不信感を抱くのは当然です。被害を与えた側こそ、そのことを記憶しなければならないのです。加害の歴史を共有しないままでは、日本は愚者の楽園という烙印を押されてしまいかねません。
とても素朴で単純なことですが、日本人が加害の歴史を知っているだけで、相手の反応はまったく変わってきます。歴史認識は完全に一致しなくても、基本的な信頼関係を築くことができます。相手も日本の戦後世代に直接の罪があるとは考えていません。まず、加害の歴史を知っていることが対話のきっかけとなります。つまり、歴史を知るということが、応答可能性という観点でも戦後責任を果たす上での第一歩となるのです。
沖縄への応答
戦後責任では、沖縄に対する応答も問われています。日本社会は、自身が負うべきさまざまなリスクを沖縄に肩代わりさせ、それを現状でも続けています。これは過去にあった加害行為ではありません。現在進行形の加害行為です。今年6月に開かれた県民大会で共同代表の玉城愛さんは、本土に住む人々を第二の加害者であると名指ししました。こうした批判も当然だと思います。玉城さんはこの言葉に続けて、「沖縄に向き合ってください」と訴えかけました。日本社会はこの呼びかけに対して応答しなければなりません。安倍政権はこの呼びかけを無視して暴力的な対応を続けています。
大切なのは勇気
いまの日本社会は、戦後50年より状況が悪くなっています。経済的な格差が広がり、政治的には改憲勢力が議会の3分の2を占めるようになりました。こうした状況で戦後責任に向き合い、周辺国との安定した関係を構築する展望を描くのは簡単ではありません。
ただ、その中でも諦めたり、へこたれたりしてはいけません。いま私たちに求められているのは勇気だと思います。平和を訴えることが社会の雰囲気に押され、気後れしてしまうような状況にあっても、発言や行動を続けること。大切なのはそうした勇気ではないでしょうか。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

