「第四次産業革命」と労働運動「インダストリー4.0」と労使関係
中小・請負問題に目を向けよ

「インダストリー4.0」の真のねらい
「第四次産業革命」を巡るいまの議論は、IoTやAIといった技術革新だけに捉われ過ぎです。この議論の背景には、事業の効率化や国際競争力の向上といった企業の問題意識がベースにあることを理解する必要があります。この視点を抜きに、「技術革新で働く人がマニュアル労働から解放される」と語っても、誤解を招くだけでしょう。
そもそも、「第四次産業革命」=「インダストリー4.0」という動きが、なぜドイツで出てきたのかを理解しておく必要があります。ドイツ経済の根幹は、自動車や工作機械などの製造業です。日本とアメリカは、その最大のライバルであり、日本はこの分野でいまもトップの競争力を維持しています。ドイツはこの分野での競争力の向上をねらっています。「インダストリー4.0」のねらいは自動車・工作機械産業で日本企業と対抗することなのだと認識しておく必要があります。
日本の自動車・工作機械産業の強みは、現場での競争力の強さだと言われてきました。経営学者の藤本隆宏氏は、その強さの要因を、さまざまな分野での情報交換が密であることだと説明しました。それは、製造現場の「班」の中で従業員が密に情報を交換し、さらに「班同士」が情報を交換すること。それをさらに「ライン間」で共有し、その上の「部門間」で共有し、というように、研究開発から販売部門まで、それぞれの部門間で網の目のように情報を交換するという仕組みのことだと指摘しました。そこに企業内労働組合や、グループ企業も加わり、密接な関係をつくりあげる。それが日本の製造業の強みなのです。
労働現場はどう変わるのか
「インダストリー4.0」とは実は、この密接な連携関係をITによって生み出そうとするものです。例えば、製造現場では、ラインの末端にまでインターネット機器を設置して、「知的熟練」をデジタルデータとして集積し、従業員間で共有させます。製造ラインの労働者は、ブルートゥースの端末を身に着け、蓄積された「知的熟練」のデータに基づき、一つ一つの動作をこなします。このように、ドイツが考えているのはアナログで行われていた情報交換を、ネットワークを用いながら生み出そうということなのです。その活用方法は、企業内にとどまりません。パートナー企業や下請け企業、個人請負労働者との連携も含みます。
蓄積されたデジタルデータは、企業連携のトップに立つ企業に集められます。この企業がやることというのは、こうしたデータを活用し、市場のニーズを把握することであり、アイデアを発想し、工程を管理し、連携関係を調整することです。トップの企業は実際にモノをつくる工程に携わることはありません。そのほとんどをアウトソースするわけです。
では、こうした構図の中で、末端で働く労働者の環境はどう変わるでしょうか。ドイツの労働組合は、末端の労働者にもITの技術・知識がより求められるようになると労使交渉の中で訴えています。しかし、果たしてその通りになるでしょうか。それは幻想に過ぎないと私は考えています。むしろ、より単純化された労働が広がる可能性すら指摘できます。
確かに、製造ラインの末端にまでインターネットが媒介することで、労働者はその機器を操作するための技能が求められるようになるでしょう。しかし、その技能水準は、アプリそのものを生み出すほどの技能ではないはずです。機器を操作するための技能水準がどの程度になるのか現状ではわかりません。それでも、すべての人が高度な知識や技能が必要になるとまではいかないということです。
「クラウドワーク」が意味するもの
IoTやAIといった技術革新が進んでも、単純作業を担う労働者や中小企業は必ず存在します。しかし、そのことが「インダストリー4.0」の中で、語られることはほとんどありません。
「インダストリー4.0」の中でドイツの経営者は、「クラウドワーカー」の創出について言及しています。会社に所属せず、雇用されずに働く人が増えるだろうということです。経営者がこうした「請負労働者」を活用しようとする動機は、市場ニーズや経営環境の移り変わりのスピードが速くなり、プロジェクトが短期化することで、特定のスキルを持った人材を企業内で継続して雇用することが非効率になっていることから生まれています。企業は、そうした人材を社内に固定せず、社外から確保したいと考えているのです。
ただし、注意してほしいのは、「コア」となる人材は、企業内にがっちり残しておくということ。「コア」になる人材とは、ニーズを把握する人、アイデアを発想する人、企業間の連携を調整する人─などです。こうした「コア」人材以外の労働者や機能は、企業外に置く。こうした動きが世界中で展開されています。
アメリカにおけるシェアリングエコノミーの広がりは、この典型的な事例だと言えます。例えば、タクシー配車サービスの「ウーバー」は、事業の全体像を構想するだけで、運転手を雇用することはありません。かつて、「フォード」は自社内に発電施設や製鉄工場まで持っていました。しかし現代のグローバル企業は、アイデアを生み出すコア部分は企業内に残していても、それ以外の機能はすべてアウトソースするようになっているのです。そうすることで、事業リスクを最小化し、利益を最大化させようとしています。
同じ構造は日本についても言えます。製造業における期間工を「クラウドワーカー」だと考えてみてください。どの企業も経営環境の変化に柔軟に対応します。日本における大企業と中小企業の関係を思い出してください。大企業にとって中小企業との関係は、取引コストを抑制する一つの手段でした。日本の産業界もアメリカと同様に本体をスリム化させる動きは、以前からあったのです。私たちはこのことを見つめ直す必要があります。
アメリカの労働組合の苦難
こうした事態にアメリカの労働組合はどう対応しているのでしょうか。いまのところ、クラウドワーカーの組合員はアメリカにはいません。その対応は後手に回っているのが実際です。
アメリカでは請負労働者の団体に、団体交渉権が認められていません。結社の自由はありますが、交渉すると独占禁止法の適用対象となってしまうのです。運輸関係の労働組合が「ウーバー」の請負労働者の組織化に乗り出していますが、団体交渉権を持つには至っていません。シアトルやロサンゼルスでは、団体交渉権を視野に入れた、団結権の付与について議論が始まっています。製造業では、工場における請負労働者化が進んでおり、自動車部品メーカーでは時給8ドルで働く請負労働者が増えています。
これに対して政府はクラウドワーカーの退職金や年金制度について動きを見せ始めたばかりです。クラウドワーカーが実際にどれくらいの規模でいるのかも把握されておらず、来年に調査することが決まったばかりです。このように、加速化する請負化の動きに対して、政府も労働組合も対応が追い付いていません。
日本の産業構造を見つめ直す
今後、クラウドワークや請負化が進めば、雇われて働くことに基づく労働組合は、根拠を失うことになりかねません。労働組合にとって非常に深刻な問題だと言えるでしょう。
アメリカの労働組合は、こうした事態に対応するため、垂直的な連携のトップにいる企業に対して、使用者としての責任を認めさせる運動を展開し始めました。一つの例では、アマゾンからアウトソースされた倉庫で働いている労働者の雇用責任をアマゾン本体に認めさせようという運動です。
これを日本に置き換えて考えてみましょう。前述のように日本にはもともと大企業と中小企業のような元請け下請け関係がありました。この関係を見つめ直す必要があるのです。労働運動としては、これまで以上に中小企業の労働条件について、真剣に考える必要が出てくるでしょう。
「インダストリー4.0」に関して、問題は技術革新の流れに乗り遅れるか否かではないのです。その背景に、企業の効率化や国際競争力の向上というねらいがあることを見過ごしてはいけません。中小企業との格差や個人請負といった古くて新しい問題を避けていては本質を見誤ります。たとえ、請負化が進んでも、経営に協力する労働組合の必要性がなくなることはないでしょう。企業も労働組合の力を必要としているのです。しかし、それでは、コア人材だけの労働組合となり、政治的な影響力も小さくならざるを得ません。
社会的な意義を労働運動が持ち続けるためには中小企業との格差問題や個人請負の問題は、避けて通ることのできない、これまで以上に注力すべき問題となっているのです。
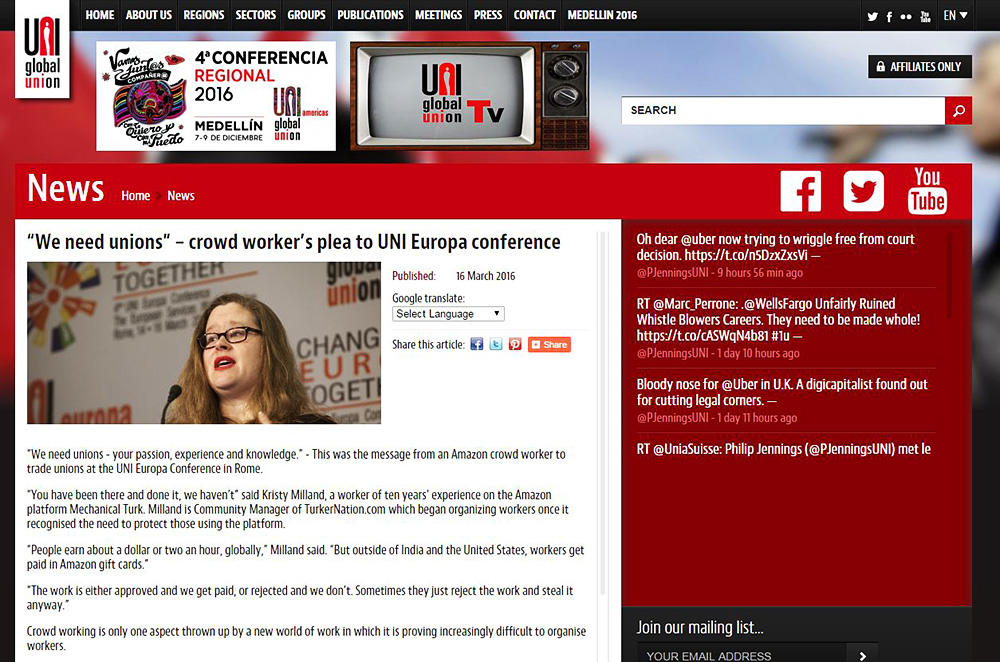
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

