労働組合の機関紙は「朝日新聞的」であれ
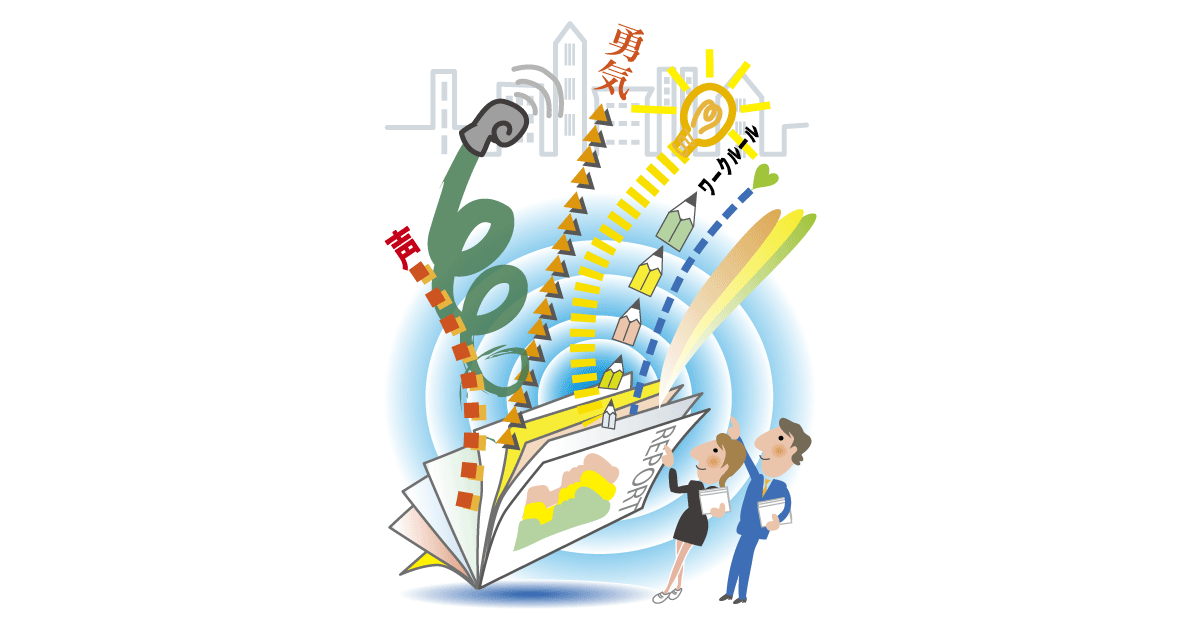
「『かもめ』はリクルートの朝日新聞」
リクルート創業者の故・江副浩正氏はこんな言葉を残している。『かもめ』とはリクルートの社内報だ。朝日新聞の報道でリクルート事件が明るみに出て、ついには江副氏の逮捕にまでつながったのは実に皮肉だった。ただ、社内の経営に対して批判的な意見も含めて掲載するという姿勢は評価したい。もちろん、それがガス抜きのためだったとしてもである。
私が同社に在籍していた90年代後半から00年代の前半、江副氏は経営から完全に退いていたが、社内報には「社内朝日新聞」の空気が充満していた。エース社員による経営批判コメントは毎号のように掲載されるし、他社のエース社員との座談会まで掲載され、自社がいかに世間の波から遅れているかの問題提起も行われていた。社内報でほえた社員の中には抜てきされた人も多数いた。
社内報と労組機関紙はまた違う。そもそも発行する主体が違う。社内報は、広報部などが経営側の論理でつくるものである。
労組機関紙は文字通り、労働組合が発行するものである。この時点で労組機関紙の目的は明確なはずである。組合員のための媒体であるべきだ。労組の動きを伝えるだけでなく、組合員にとって有益になり得る雇用・労働に関する社会の動き、ワークルールの知識などを伝えるべきだし、組合員の声を吸い上げ、共有するメディアであってほしい。
この媒体は、市販される類いのものではない。だからこそ、できることに注目したい。
新潮社の『新潮45』という媒体の休刊騒動は記憶に新しい。自民党の杉田水脈衆議院議員の「LGBTは“生産性”がない」という内容の寄稿を掲載。批判が殺到していたが、さらに同議員を擁護する特集まで組み、怒りの声を受け、すぐに休刊が決まった。同誌の部数は、全盛期で5万7000部だったが、最近の号では1万6000部程度に減っていた。数年前から嫌韓・嫌中、反朝日新聞などの記事に活路を見いだしていた。休刊に至った特集も、申し訳ないが新潮社とは思えない雑なものだった。
商業誌は、どうしても部数を維持、拡大しなくてはならないという競争にさらされる。労組機関紙には、この部数のプレッシャーがない。もちろん、組合費を原資に発行しているがゆえに、コスト意識が必要なのは言うまでもない。ただ、部数の維持・拡大のための延命策を考える必要が商業誌に比べて少ない。腰を据えて、意義のある問題提起を行うことができる。
あくまで要望ではあるが、商業誌ではできないような、長期にわたる調査などにトライしていただきたい。中長期でまとめあげれば、貴重な資料になり得るし、社会を動かすからだ。何より、組合員の味方であってほしい。つらい思いをしている労働者に、問題を解決するヒントや勇気を与えるものであることを祈ってやまない。労働者にとって、よりよい労働環境をもたらすようなオピニオンを発信してもらいたい。利益と合理性の権化であるようなリクルートですら「社内朝日新聞」を容認した。労組機関紙はとことん朝日新聞的であってこそ健全なのだ。

![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

