つながりを生むレク・文化活動を考える
労働組合「レク」図鑑!笑いで職場を楽しくしよう
効果的なユーモアの活用方法とは?

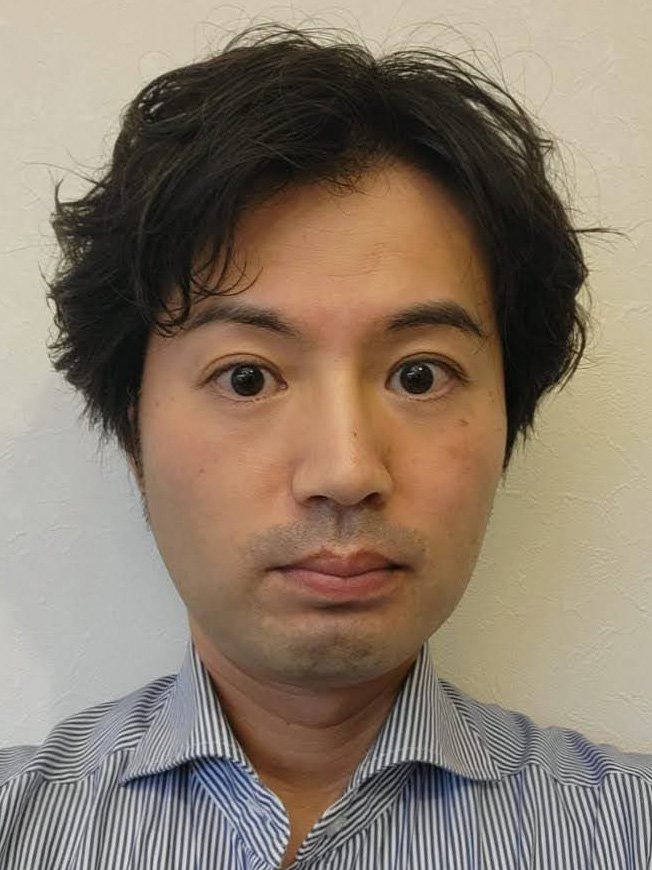
職場の笑いの効果
2022年にアメリカのギャラップ社が行った幸福度調査があります。この中に「昨日たくさん笑ったか」という項目があり、日本は77%でアメリカより1ポイント高いという結果でした。日本人が笑っていないかというとそうではないようです。
これとは別に私が行った研究で「どこで笑っているか」を調べたことがあります。その結果、職場よりもプライベートで笑うことが多いことがわかりました。プライベートではほぼ毎日笑っている人は45%でしたが、職場では24.4%でした。接客や営業など対人関係の仕事をしている人は、仕事の中で笑うことも多いように思えますが、本心からの笑いではなく、笑いの自覚がないために数値に表れないのかもしれません。
アメリカでは職場の笑いに関する研究が多く行われています。それらの研究では、笑いにはストレスを緩和したり、乗り越えたりする効果があることが確認されています。
また職場の笑いは、イノベーションに関連するともいわれています。くだらないと思えるようなことを発言できる職場環境だからこそ、心理的安全性が向上し、いざという場面で思ったことを発言しやすくなり、イノベーションに結び付きやすくなるということです。このように職場の笑いは科学的にも効果があるとされています。
ユーモアの活用
笑いには、自分が笑うという受動的な行為がある一方で、自分が相手を笑わせるという能動的な行為もあります。日本では、お笑い芸人のネタで笑っても、自分が他人を笑わせることに自信がない人が多いのではないでしょうか。
同時に、日本では職場でユーモアを活用しようとする姿勢も強くありません。対照的なのがアメリカです。アメリカでは職場を含め、さまざまな場面でユーモアが活用されています。例えば、初対面の人と会うときに緊張を解きほぐしたり、自分を印象付けたりするために積極的にユーモアが使われます。
アメリカでは、ユーモアセンスには笑わせる言動のほかに、三つの側面があるといわれています。それが、(1)活用、(2)発見・気付き、(3)記憶─の三つです。
(1)の活用は先ほど述べたように、緊張やストレスを緩和したり、自分を印象付けたり、さまざまな場面で活用されます。ポイントは、意識してユーモアを活用していることです。
(2)の発見・気付きとは、日常の中の面白さに気付くことです。例えば、他人との何気ない会話の中にある面白みに気付くこともユーモアセンスの一つとされています。面白さに気付くことはとても大切で、この発見や気付きがあることで相手に対する理解が深まったり、感じ方が変わったりします。面白さに気付くことは日本でもお笑い芸人の仕事の一つだったりします。
(3)の記憶は、過去の経験を覚えておくことです。「そんなことよく覚えているね」という意外性が笑いにつながることはよくあります。2回目に会う人でも前回会った時のことを覚えていると話に弾みがつくと思います。
アメリカでは、ユーモアセンスの側面をこのように捉えつつ、意識的に活用しているのです。
日本の笑いの特徴
日本の笑いの特徴の一つは、「身内ウケ」が多いことです。「身内ウケ」は、組織内部の人にはウケるかもしれませんが、初対面の人や組織外の人を笑わせるとなると難しくなります。私が行った調査でも組織外の取引先に冗談を言える人の割合は多くありませんでした。
日本の笑いのもう一つの特徴は、「上から下」への笑いがとても多いことです。発話に関する研究では、発話する権限を持つ人は階層が上の人が多く、ユーモアに関しても役職に就いている人や権限のある人はユーモアを活用できる一方、階層の下の人はそうではないといわれています。つまり、日本では笑いがトップダウンの傾向にあるということです。
こうした特徴は場合によってはハラスメントになることがあります。笑いにはどうしても攻撃性が含まれるものなので、言ってもいいのかどうかを考えてから発言する必要があります。また、組織の笑いは、階層が上の人の志向に影響されます。そのため上の階層に上がる際は自分の笑いの好みを立ち止まって考える必要があると思います。
笑いは、組織の日常のコミュニケーションを反映します。愛想笑いが多かったり、上司へ忖度が多かったり……。笑いのあり方を分析することで、組織の状態をチェックすることもできます。組織の状態を知るためにも笑いに注目することができます。
笑いのセンスを身に付ける
日本では、笑いというと「お笑い芸人」のものになってしまって、一般の人に求められるハードルが高くなっているように感じます。ただ、笑いについてそんなに難しく考える必要はなく、まずは自分のエピソードや体験談を簡単に話せるようになればいいと思います。スベッたらどうしようとか、失敗したらどうしようとか考えていると発言できなくなってしまいます。面白くないように思える話こそ、周りのフォローが大切です。
笑わせるネタもアドリブである必要はありません。アメリカ人もアドリブのユーモアで笑いをとろうとしているわけではなく、典型的なジョークをたくさん覚えて、引き出しに入れておき、必要な場面でそれを取り出すことをしています。例えば、立川談志が集めたジョーク集には、次のようなものがあります。
患者「先生、私初めての手術なもんですから、とても心細くて心配なんです」
医師「お気持ちはよくわかります。実は私も初めての手術なんです」
こうした典型的なネタをいくつも覚えておいて必要な場面で活用します。その意味で、ユーモアは多くの人が手に入れられるスキルだと思います。アメリカでは、職場のユーモアに関する研修などもビジネスになっています。ユーモアの知識が共有されることで職場でも活用しやすくなるはずです。
日本では、笑っていい場とそうではない場の区別がはっきりしています。しかし、アメリカではそうではなく、会議の場でもまじめな話をしつつ、ユーモアを交えます。職場にもっと遊びの要素を増やしてもいいのではないでしょうか。
笑いは、雑談でこそ生まれやすくなるため、職場での雑談を大切にすることが重要だと思います。最近の職場は、効率が重視され雑談も少なくなりつつありますが、同じ職場で働く同士でユーモアを言い合えるような関係であった方が、実は効率的で、創造性も高まると思います。組織として、そうした環境をつくれるかどうかが大切です。より働きやすい職場をつくるという意味で労働組合の皆さんにも笑いに着目してほしいと思います。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

