中小企業の春闘はここから
〜「格差是正」「底支え」へ中小の人手不足の解消へ
特定最低賃金の活用を
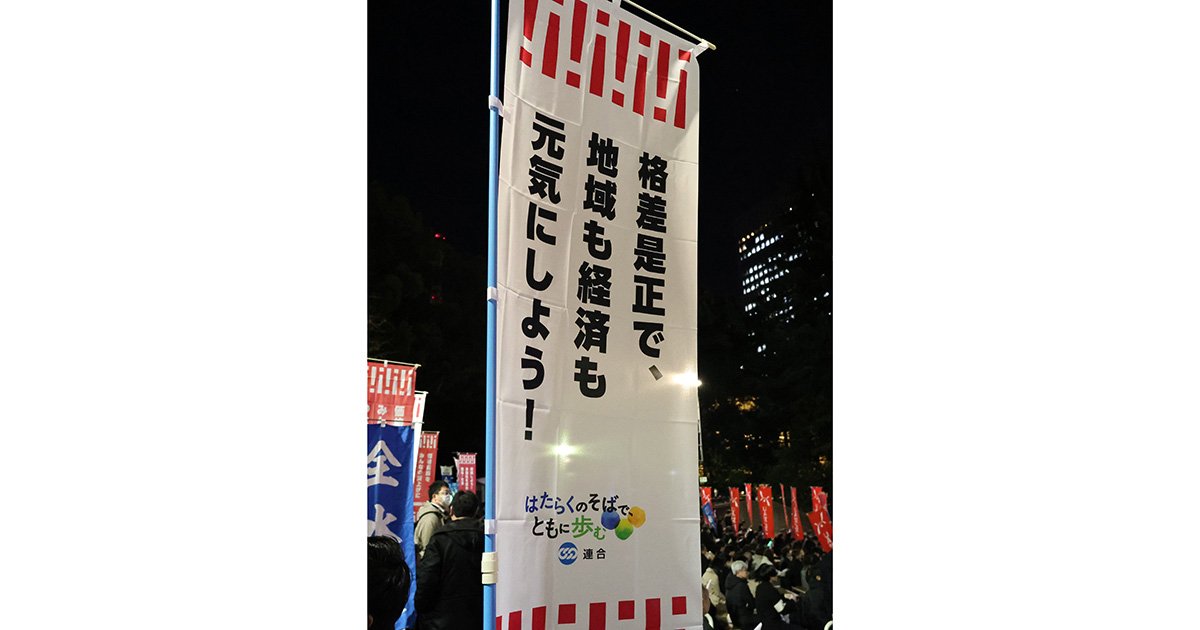
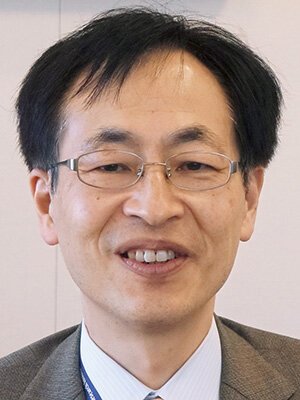
──中小企業の賃上げ状況をどう捉えていますか?
東京商工リサーチの調査によると、2025年度に賃上げを予定している企業は85.2%に上り、賃上げの動きが広がっています。一方、大企業と中小企業の賃上げ率には格差があります。連合が集計した2024春闘の平均賃上げ率は、従業員1000人以上の大企業は5.24%、300人未満の企業は4.45%でした。
ただ、あまり知られていないこととして、従業員一人当たり平均の賃金上昇率は中小企業の方が高いという実態があります。これは大企業の賃上げが若手中心で中高年はあまり行われていないのに対し、中小企業では若手が入社せず平均年齢が高まっているためです。大企業は若手の賃上げを進めつつ、全体の人件費をコントロールしているのに対し、中小企業は若手を確保できず、賃金が相対的に高い中高年の割合が高まって、人件費負担が重くなっています。
こうした状態は、労働分配率にも表れています。大企業は賃上げ率が高くても労働分配率は下がる一方で、中小企業は賃上げ率が低いのに分配率が高止まりしています。
──中小企業の賃上げを実現するためには何が大切でしょうか。
まずは生産性を高める努力をすることが大切です。そのために製品の品質を上げたり、価格転嫁できる力のある製品やサービスを生み出したりすることが求められます。
その一方で日本は、アメリカやドイツと比べて価格転嫁が十分に進んでいません。特に、原材料費や労務費の比率が高い中小企業は、適切な価格転嫁ができなければ経営が厳しくなります。価格転嫁をしやすい環境を政府が継続的に整備することも大切です。
──特定(産業別)最低賃金はどのような役割を果たせるでしょうか。
政府が引き上げを進めている地域別最低賃金は、すべての企業に適用されるため、生産性の低い企業にどうしても合わせざるを得ない面があります。
一方、特定最低賃金は、地域や業種の実情に応じて金額を設定することができるため、生産性の高い分野に合わせて賃金を引き上げることができます。これは労働組合が特定最低賃金の意義としてよく用いる理屈です。
もう一つ、私が特定最低賃金の活用を訴える理由があります。それは、特定最低賃金が、中小企業の人手不足の解消に役に立つということです。
現在、中小企業では人手不足が深刻化しています。採用をしたくても人が集まってこないため、余力がなくても賃上げをせざるを得ない「消極的賃上げ」が広がっています。こうした状況を逆手に取り、特定最低賃金をうまく活用すれば、中小企業の人材確保につながる可能性があります。
重要なのは、特定最低賃金の活用に合わせ、企業横断的な生産性向上を地域で実現することです。政府はこれまで、最低賃金の引き上げに伴う生産性向上の支援策を企業に提供してきました。ただし、それは個別企業での利用が基本で、利用する企業は一部に限られていました。
特定最低賃金を活用することで、より「面的」な支援が可能になります。例えば、ある地域の観光業や飲食業に特定最低賃金を適用したとしましょう。すると、その賃上げを実現するためには、業種全体の生産性向上を支援する必要があります。そこで重要なのは、地域のブランドづくりの推進や、企業横断的なITシステムの導入といったより「面的」な支援策です。そうした支援を展開することで、地域全体の競争力が高まり、それが中小企業の人材確保にもつながります。
特定最低賃金はこれまで、地域別最低賃金に屋上屋を架すものとして不要論が出ていました。しかし、それは人材確保が容易な時代の議論でした。現在のように人手不足の局面では、人材を確保するためには賃金を上げざるを得ません。その中で、特定最低賃金と地域の業種全体の生産性向上にセットで取り組むことで、人材確保や地域の活性化に結び付けることができます。これは企業にとってもメリットのある話です。
こうしたメリットを生かすためには使用者側のヨコの連携も欠かせません。労働組合としては、こうした利点を使用者側に説明し、企業間のヨコの連携を促すことが重要になるでしょう。
──特定最低賃金の課題はどこにありますか?
一つは、申し出要件のハードルが高いことです。
特定最低賃金には、「労働協約ケース」と「公正競争ケース」があります。前者の「労働協約ケース」は、新しい特定最低賃金を決定する場合の申し出要件として、(1)基幹的労働者の2分の1以上が労働協約の適用を受けること、(2)労働協約の当事者の労働組合または使用者の全部の合意により行われる申し出であること──という二つの要件を設けています。
特定最低賃金の活用を図るためには、こうした申し出要件のハードルを下げることがまず考えられます。あわせて申請手続きの簡略化も検討すべきでしょう。
ここで述べたのは議論をするための申し出要件なので、具体的な範囲や金額の水準は、その後の労使の話し合いの中で決められます。まずは話し合いのためのハードルを下げることが大切だということです。
──特定最低賃金が、地域別最低賃金に追い抜かれる現象も起きています。
地域別最低賃金は現在、政府の政策によって引き上げが進んでいます。しかし、政府の意向による引き上げが進み過ぎると、実態との乖離が生じ、最低賃金が守られなくなるリスクが生じます。最低賃金を適切に機能させるためには、使用者サイドの納得も必要です。
地域別最低賃金は、相対的貧困の解消や格差是正といった社会政策的な役割が強いのに対し、特定最低賃金は労使の話し合いによる賃金と生産性の引き上げという性格を持っています。政府は、地域別最低賃金を産業政策的に活用していますが、その発想に基づくならば、特定最低賃金の方が適しています。
特定最低賃金のこうした性格を踏まえれば、その水準は地域別最低賃金のプラスアルファというだけではなく、競合している地域や産業との比較や、その業種における生産性の高い企業を指標とすることなども考えられます。
──労働組合にできることは?
中小企業の賃上げに向けて大切なのは、一つ目は、賃上げのためのパイを増やすこと。生産性を上げるために労使が前向きに協力することが大切です。ただし、それだけだと使用者の目線と同じになってしまうので、二つ目は、公平な分配を訴えることです。
特定最低賃金を活用するためには、地域における労働組合のヨコの連携が欠かせません。加えて、未組織労働者や非正規雇用労働者との連帯も重要になります。特定最低賃金の範囲が狭すぎれば効果は望めません。さまざまな労働者との連携が重要になると思います。
人手不足の局面において、生産性の向上と賃上げ、さらには地域の活性化を同時に実現させるために特定最低賃金の活用を進めてほしいと思います。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

