どうする? 社会保障
めざすべきビジョンを再考する社会の分断を防ぐため
「第3の財源」の議論を


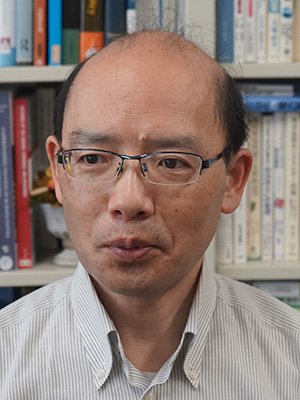
手薄だった「人生前半の社会保障」
「103万円の壁」の引き上げに伴う、7兆〜8兆円規模の減税を含む政策が有権者の支持を集め、それが政党支持率にも目に見える形で反映されたことは、これまでにない新しい現象です。従来であれば無風状態で国会を通過していた予算に対して、今回は報道量も非常に多く、税の問題を多くの人が「自分ごと」として受け止めたのだと思います。
「壁」を引き上げたら労働供給が増えるのかという問題はひとまず置くとして、減税が支持される理由も理解できます。現在は物価上昇で実質賃金が目減りしており、家計の負担を減らすためにも減税を求める声が強いのだと思います。
また、減税を求める声が強いもう一つの理由として「自分は国から給付や支援を受けていない」と捉える現役世代が多いこともあると思います。社会保障を受益していないという現役世代の感覚が、減税の支持につながっているのではないでしょうか。
実際、社会保障に関する支出を見ると、日本は医療や年金、介護などの高齢者向け支出の割合が高く、高齢化に伴い関連支出が増えており、それが財政膨張の原因になっています。これに対して教育に関する社会支出の割合は他国に比べて低く、公教育にお金が使われていません。こうして現役世代や若年世代の受益が小さい中で、彼らは消費税率の引き上げや社会保険料負担によって所得が削られる感覚を持っています。こうした状況が減税を求める背景にあるのだと思います。
これまでも指摘されてきたように日本の制度は、「人生前半の社会保障」が手薄でした。現役世代にも就職難や不安定雇用、失業などのさまざまなリスクが存在します。それらのリスクに対して、家族手当や住宅手当、失業給付、職業訓練などの支援が本来必要でしたが、十分な体制が構築されませんでした。非常に罪深い課題だと思います。
消費税と社会保険料の限界
「人生前半の社会保障」を充実させようとしても、財源の問題があります。国債をもっと発行すればよいという考え方がある一方、財政均衡に配慮すべきという考え方もあり、そのせめぎ合いの中で、世代間の財源の奪い合いともいうべき現象が起きています。高額療養費の上限額の引き上げは、その典型といえます。
こうした奪い合いの状況を放置すると日本社会が分断に追い込まれるリスクが高まります。その結果、排外主義的な動きの強まりも懸念されます。
現実的には国債の発行だけで社会保障を充実させることは困難です。そのため、財源に関する議論をする必要があります。しかし、消費税や社会保険料を引き上げることにも困難がつきまといます。消費税の引き上げは、低所得層の医療窓口負担の軽減などに役立てられていますが、実質所得が上がらない現状では、その引き上げは政治的に極めて難しいといえます。また、社会保険料に関しても、その対象は賃金であることから、そこに頼る仕組みにも限界があります。
「第3の財源」の議論
こうした現状を踏まえれば、消費税でも社会保険料でもない「第3の財源」の導入について真剣に議論する必要があります。
その先例の一つとして参考になるのが、フランスの一般社会拠出金(CSG)です。これは、1991年に社会保障への支出を目的に導入された税制度です。「第2所得税」とも呼ばれ、賃金などの稼働所得だけでなく、年金などの代替所得にも課税され、幅広い世代から税を徴収します。さらに資産所得や投資益、くじやカジノでの獲得金にまで幅広く課税するところに特徴があります。
もう一つの例は、オバマ政権下で導入された投資純利益税です。これも投資益などの金融所得が課税対象になります。
こうした制度の導入によって、アメリカとフランスでは税収が増加しました。特にフランスでは、CSGが累進所得税を上回る税収をもたらしています。
一方、日本では、岸田政権が金融所得税の引き上げを掲げたものの、世論からの反発で断念しました。金融所得課税の税率は民主党政権時代に10%から20%に引き上げられましたが、当時それほど反発はありませんでした。現在は「新NISA」で非課税枠が拡大し、多くの人は税率引き上げの影響を受けませんが、それでも反発はあるかもしれません。
他方、日本では、2023年度の税制改正で「ミニマム税」が導入されました。これは、金融所得を含め、すべての所得を合算し、3億円以上の所得を得ている人を対象とし、その上で各種の控除を適用した後の実質的な負担率が、所得税の最高税率である45%の半分、22.5%を下回る場合には、その差額に対して追加的に課税するという仕組みです。負担の最低ラインを設定するという意味で「ミニマム税」という名前がついています。
「人生前半の社会保障」を充実させるためにこれを拡充するのも一つの方法です。例えば、「ミニマム税」の対象となる所得の合算額の基準を引き下げたり、税率を引き上げたりすることで制度を拡充し、その税収を社会保障財源として活用することが考えられます。
このように、高所得者が事実上税負担を免れている状況を是正する制度に関して社会的なコンセンサスを得た上で、「人生の前半」に重点的に再分配を行うべきだと考えています。
社会の分断を防ぐために
問題は、そうした制度の導入に向けたコンセンサスをどう得るかです。減税への期待が強い中で、高所得者層への課税を含めた応能的な負担が、暮らしの不安を解消できるというメッセージを社会にどう伝えられるかが大切です。
そのためには、現役世代や子どもへの社会的支出が、単なる分配ではなく「成長戦略」であるという「人的資本投資」の論理を打ち出していくことも効果的だと思います。
また、国家という仕組みを通じて、お金の流れを是正できるという点をしっかり訴えていくことも重要です。市場で決まった所得格差をそのまま放置すれば、格差は拡大し続ける一方です。しかし、税を通じて負担を分かち合うことで、社会保障や子育て支援、学校教育といったセーフティーネットが整備され、再分配が可能になります。こうしたセーフティーネットが整えば、教育や医療、保育などの無償化が進み、個々の負担も軽減されていきます。
このように、税を単なる「負担」として捉えるのではなく、社会全体を支える仕組みとして捉え、丁寧な議論をする必要があります。市場で生じた格差を放置してよいのか。社会の分断を防ぐためにも、そうした根本的な問いに立ち返ることも求められています。
労働組合にとってまず重要なのは、労働者同士の連帯を築くことです。雇用形態や世代の違いを超えて支え合う意識を醸成することがその出発点となります。その上で、税を通じた社会連帯の仕組みを形成するために、どのようなメッセージを発信できるのか考えてほしいと思います。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

