どうする? 社会保障
めざすべきビジョンを再考する現役世代への給付をどう拡充するか
フランスの仕組みから学ぶ

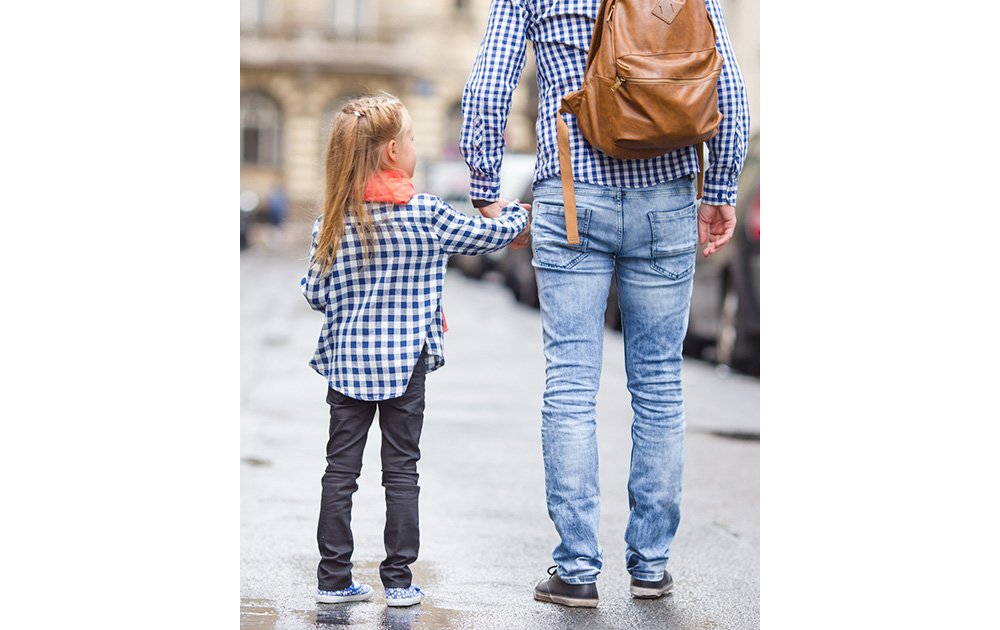

高齢・現役のバランス
国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計(2022年度)」によると、国の社会支出に占める高齢者関係給付費の割合は、61.1%でした。高齢者関係給付費とは、年金や高齢者医療、老人福祉サービス、高齢者雇用継続給付金の合計のことを指します。
2022年度の社会保障給付費は約137兆円だったので、そのうち約84兆円が高齢者向けの給付として使われていることがわかります。現役世代は税や社会保険料で社会保障を支えているため、負担は大きい一方、受けられる恩恵が少ないと感じるのだと思います。
ただし、国は現役世代向けに何もしてこなかったわけではありません。社会支出に占める高齢者関係給付費の割合は、2003〜2004年度に70.2%でピークを迎え、それ以降は低下傾向にあります。一方で児童手当や保育サービス、育児休業給付などの合計の児童・家族関係給付の割合は、2022年度で全体の7.4%まで増えました。このように国は、高齢者関係給付費の割合を低下させる一方で、児童福祉サービスの充実を進め、社会支出のバランスを一定程度、是正してきたことがわかります。
働く世代と社会保障
他方、現役世代向けの給付は、依然として少ないのが現状です。
もともと、社会保障制度は、病気やけが、高齢化などによって働けなくなった場合に備え、保険料などを負担し、必要なときに給付を受ける仕組みでした。つまり、現役世代は働いている間は自身の所得で生活することが前提でした。
この仕組みをうまく機能させていたのが「完全雇用」でした。しかし、経済が停滞し、働いても収入が安定しない、思ったように働けない、就職先が見つからないといったリスクが顕在化するようになると、「完全雇用」はうまく機能しなくなりました。こうした状況に対応し、労働市場で安定して働き続け、収入を得られるよう支援するため、職業訓練や雇用安定施策が強化されてきました。
また、労働の対価として支払われる賃金は基本的に労働者1人分です。家族を養う必要がある場合には、それを補う手当が必要という考え方から、家族手当ができました。こうした制度が現役世代向けの社会支出といえます。
このように社会保障には「働けるうちは自分で何とかする」という前提があります。そのことが現役世代の受益感の少なさや、負担感の強さにつながってきたのだと思います。
フランスの家族向け社会支出
こうした感覚を改善するためには、現役世代の受益感を高める政策が必要になります。
一つの参考になるのがフランスの「保育方法自由選択補足手当」という制度です。フランスでは、保育サービスの運営費は公的に負担されており、幼稚園は無料ですが、保育所は所得に応じた保育料がかかります。保育所の入所は、所得が低いほど優先度が高くなるポイント制が採用されているため、高所得層や中間層が自治体の保育サービスを利用できないケースも発生します。こうした場合に、保育所を利用できない人に対して200〜529ユーロ程度の「保育方法自由選択補足手当」が支給されます。手当を受給した人は、それでベビーシッターや保育アシスタントを雇います。現金給付として本人に支給されるため、給付の実感が湧きます。
また、フランスにはこのほかにも、日本の児童手当にあたる「家族手当」や、多子家族への支援である「家族補足手当」、入学などの準備にかかるお金を補助する「新学期手当」といった制度もあります。
このようにフランスでは、育児をしている家庭に直接的な現金給付があるため、中間層や高所得層にも恩恵があり、それが「自分も社会の一部として支えられているのだから、社会を支えよう」という意識につながるのだと思います。
雇用と生活を支える制度
加えて、フランスには現役世代向けに「活動連帯所得」「活動手当金」という仕組みがあります。
「活動連帯所得」は、25歳以上を対象とした最低所得保障制度であり、18歳から24歳でも一定期間働いた経験がある場合や、ひとり親である場合には受給が可能です。例えば、ひとり暮らしの場合は635.71ユーロが支給され、家族構成によって支給額が変動します。この制度には就労支援プログラムも含まれており、日本のハローワークに相当する機関を通じて、アドバイザーのサポートを受けながら就労計画を作成することが可能です。
また、「活動手当金」は、18歳以上の低所得労働者が就労を始めたり再開したりすることを奨励するための現金給付です。こうした制度は、日本のような新卒一括採用の仕組みがなく、若年層の雇用が不安定で自立が難しいという問題に対応するためにつくられました。
一方、日本には、似たような制度として生活困窮者自立支援制度がありますが、生活を支える現金給付が弱いという課題があります。雇用の流動化が進む中にあって所得保障と公的な職業訓練の重要性は高まっていると思います。
日本で参考になる仕組みは?
「保育方法自由選択補足手当」は、日本でも参考にできるのではないでしょうか。日本には、「保育の必要性の認定」を受けても認可保育所に入れなかった場合、一定額の保育料が無償化される制度がありました。フランスでは、これを現金給付として支給している点が特徴的です。フランスのように、所得に関係なくすべての子育て世帯が受給できる手当を拡充すれば、給付の実感が湧きやすくなるのではないでしょうか。
また、「活動連帯所得」や「活動手当金」も、参考になると思います。これらの制度を通じて職業訓練を受けた人材が企業に就職し、有用な人材として活躍すれば、周囲の人も制度の効果を実感できます。雇用の流動化が進む中で、日本でも職業訓練の拡充が求められています。
給付の拡充のために
強い負担感から生じる減税の訴えを変えるためには、まずは給付を拡充しなければなりません。そのために家族手当や住宅手当、不安定雇用者向けの就労支援や職業訓練、所得補助などを充実させることが重要です。それが結果的に減税よりも大きな効果を生むと納得してもらう必要があります。
「給付付き税額控除」は、そのための仕組みの一つです。それに加えて、職業訓練や社会参加をすると手当が増えるような仕組みも大切です。
不安定で複雑な状況に置かれている現在の日本では、「すべての人々への給付」に加え、「困難な状況にある人々への支援」を組み合わせた社会保障の仕組みが求められています。
労働組合には、低所得から中所得の労働者が抱える課題を集約し、社会に訴えてほしいと思います。「働いていても生活が苦しい」という多くの人々の声を社会支出の拡充へとつなげていくことは、労働組合の重要な使命の一つです。
社会の問題は、個人の力だけでは解決できません。そのため、多様な声をまとめ、政策に反映させる組織が必要です。労働組合は、その中でも特に重要な役割を担っています。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

