どうする? 社会保障
めざすべきビジョンを再考する介護や低年金に直面する「就職氷河期世代」
支え合いの社会はつくれるか
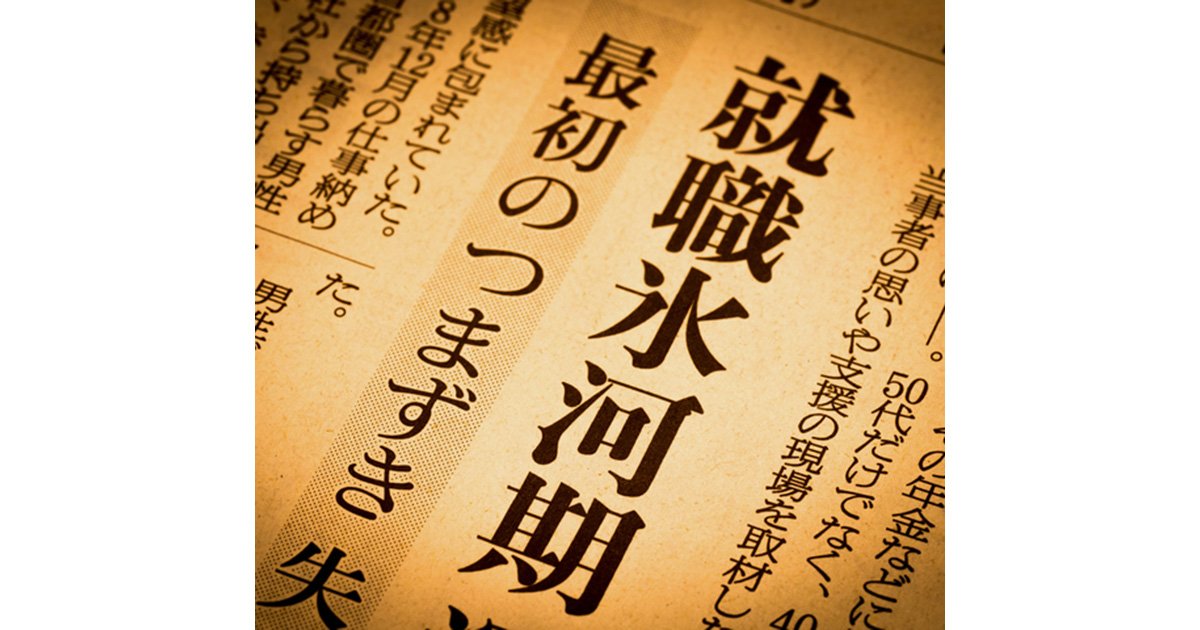
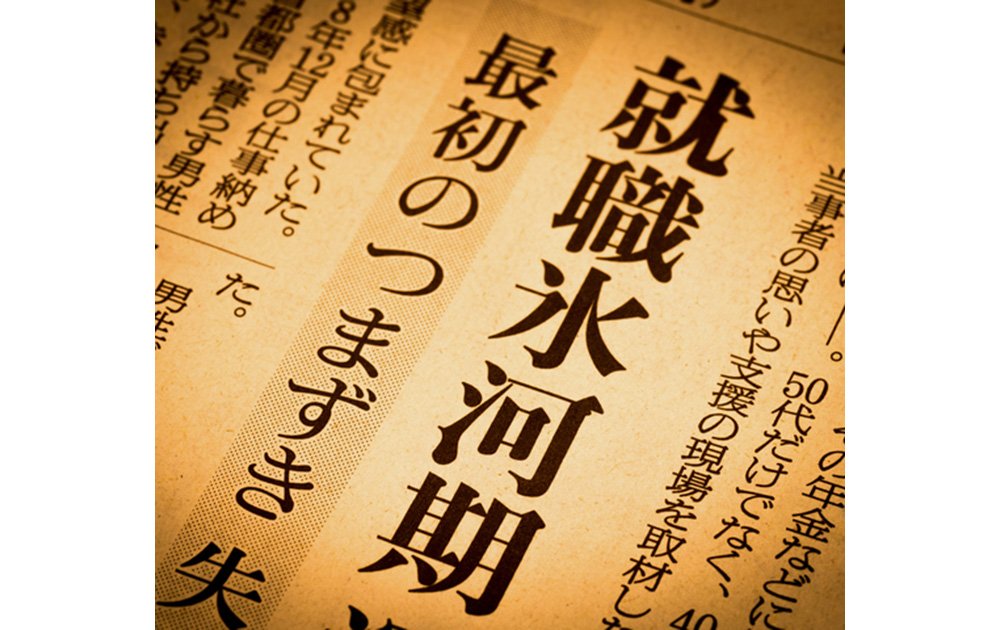

──不安定雇用のまま中高年になった「就職氷河期世代」の現状をどのように捉えていますか?
「就職氷河期世代」は50歳前後になり、親の世話や介護が必要になる人が急激に増えています。親のケアに追われ仕事がしにくくなる人もたくさんいます。
私が取材した50代前半の男性は、最初は地方の量販店の正社員として就職しましたが、過労で体を壊し、その後、非正規雇用の仕事を転々としてきました。父親が亡くなった後は、80代の母親の世話をしています。母親は体が弱っており、買い物の手伝いや病院への付き添いが必要です。そのために年休を取ることもあります。年休がなくなると給料が減ってしまうので、自分の体調にも気を付けないといけません。市役所の会計年度職員として働いていますが、月の手取りは約17万円。親の年金と合わせて生活を何とかやりくりしています。
もうすぐ50歳になるシングルマザーの女性は、両親が離婚して別々に暮らしているため、それぞれの介護をしなければいけません。派遣でコンスタントに働いていれば日々の生活はなんとかやりくりできますが、親の世話が必要になるとフルで働くことができず、収入が減ることもしばしばあります。
介護保険は、保育と異なり家族の収入が考慮されません。その結果、非正規雇用で働いている方が介護の負担が重くなり、仕事を辞めざるを得ない人もいます。制度の落とし穴というべき問題があります。
──「氷河期世代」の状況は良くなっているといえるでしょうか?
新卒初任給のアップがニュースになり、若手にとっては「売り手市場」ですが、「就職氷河期世代」を採用するメリットは企業にとってあまりなく、この世代は今も抜け落ちた存在だといえます。
「就職氷河期世代」の採用のためには、OJTのような丁寧な教育訓練が必要ですが、それをする民間企業は多くありません。多くの企業は、初任給を上げて若手を何とか採ろうとしています。統計的にも氷河期世代の賃金の伸びは、若年世代よりも小さいことが明らかになっています。このように見ると状況は良くなっているとはいえません。
──近い将来、この世代の「低年金」問題も懸念されます。
日本総合研究所の下田裕介氏の研究によれば、就職氷河期世代の中で将来的に高齢貧困に陥る可能性がある人は約135万人と推計されていて、これらの人々が生活保護を受給し、平均余命まで生きた場合、その総額は約27兆5000億円になると試算されています。そうなった場合、国が生活保護費を抑制する可能性もあります。
例えば年金が月6万円程度しかなければ、不足分を働いて補うしかありません。現状でも働く高齢者が増えていますが、その傾向は今後さらに強まるでしょう。
しかし、健康であればまだしも、50歳を過ぎてから建設や介護の仕事に就くのは体力的に厳しいという課題もあります。これらの仕事は社会的な需要があるものの、就職氷河期世代の年齢やスキルと合わないケースが多く、結果的に問題の解決にはつながりにくいのが現状です。
こうした状況を改善するには、行政が雇用の受け皿となることが重要ですが、国や地方は公務員の定数削減を進めてきました。この方針を見直さなければ、問題の解決は難しいでしょう。
──小林さんが話を聞いた「氷河期世代」が社会保障に期待することは?
すでに諦めていて、何も期待しないという人が多いです。ただよく話を聞くと、社会保障のニーズがあることがわかります。例えば、親の介護や世話がある場合に介護休業を使いやすくしてほしいとか、公営住宅に入りやすいようにしてほしいとか。物価が高くなっているので食糧費をどうにかしてほしいという声も多いです。
──税金を下げてほしいという声もあるのでしょうか。
所得が低いと減税などによって戻ってくるお金もそれほど多いわけではありません。そのため「手取りを増やす」といってもピンとこない人も多いようです。
それよりも減税による不利益の方が大きくなると考える人もいます。つまり減税によって税収が減ることで、医療や介護、生活保護のような自分たちの暮らしを支えてくれる社会保障がさらに抑制されると、冷めた目で見ている人もいます。
税金を下げろと言っているのはどちらかというと世帯年収1000万円クラスの人たちの方が多い印象です。
不安定雇用のまま過ごしてきた「就職氷河期世代」には、諦めや絶望の気持ちが広がっています。政治への期待はなく、声を上げて変えようとする気力も失われています。それだけ長い間、自分たちは放置されてきたという思いが強いということです。
──どのような対策が求められているのでしょうか。
「就職氷河期世代」が生まれた背景には、企業が労働者を守る仕組みの目をかいくぐってきた歴史があります。例えば、労働者派遣法を活用して労働者を使い捨てにしたり、社会保険料の負担を避けるために業務委託契約を増やしたり。こうした企業の責任逃れが、氷河期世代を生み出してきました。
そのため、企業の抜け道をいかに防ぐかが重要な課題となっています。どのような働き方であっても、企業がセーフティーネットのための費用を負担する仕組みを整えることが求められていると思います。
──「自己責任論」をどのように乗り越えることができるでしょうか。
他者への想像力が欠けている人が増えているように思います。
例えば、中学受験の取材で、自分の税金が生活保護やシングルマザーの支援に使われることを嫌がる女性がいました。その世帯は高所得で、「自分たちは多額の税金を納め、子どもの塾代に数百万円かけている。子どもも将来、優秀な人材になり、さらに税金を納めるはずだ。そのお金が低所得者の支援に使われるのは納得できない」と考えていました。
しかし、その女性が子どもが中学生になったタイミングで離婚を考え始めました。そこで改めてシングルマザーの支援制度を調べると、「なぜこの国のシングルマザー支援はこんなに乏しいのか」と、かつてとは正反対のことを言い始めたのです。このように同じ人間でも、立場が変われば、まったく逆のことを言い始めます。他者の状況を想像することが、「自己責任論」を乗り越える第一歩になるのではないでしょうか。
想像力が欠けた社会の中で、「誰にでもそうなる可能性がある」ということを、具体的かつ粘り強く伝えていくことが大切だと考えています。例えば、病気やケガ、失業、離婚といったリスクを「あみだくじ」のように一つずつ示し、本当に自分の力だけで乗り切れるのかを問いかける──そんな人生ゲームのようなシミュレーションを多くの人に体験してもらうのもいいのではないでしょうか。
こうしたリスクを認識することで、支え合う社会の大切さが見えてきます。そして、それがあるからこそ、人は安心して今を頑張ることができるはずです。
順調なときは、こうしたリスクをつい忘れてしまいがちですが、だからこそ、粘り強くこの視点を伝え続けていきたいと思います。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

