「新時代の日本的経営」から30年
雇用システムはどう変わったのか?労働組合は誰の賃金を守ってきたのか
「二重労働市場論」と日本の課題
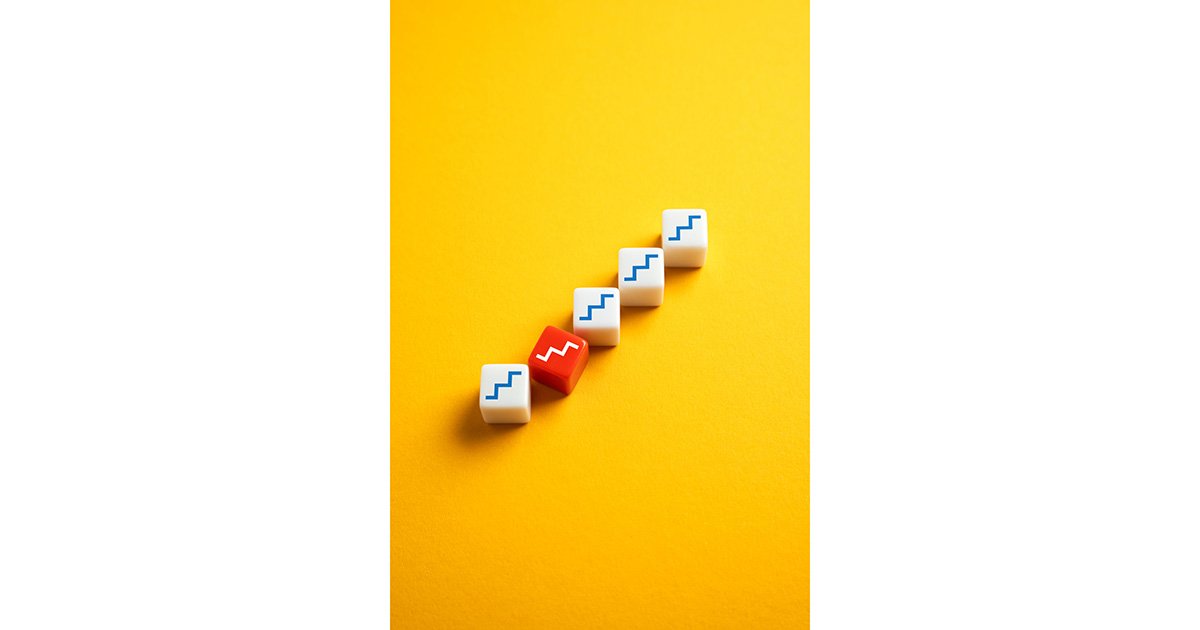

准教授
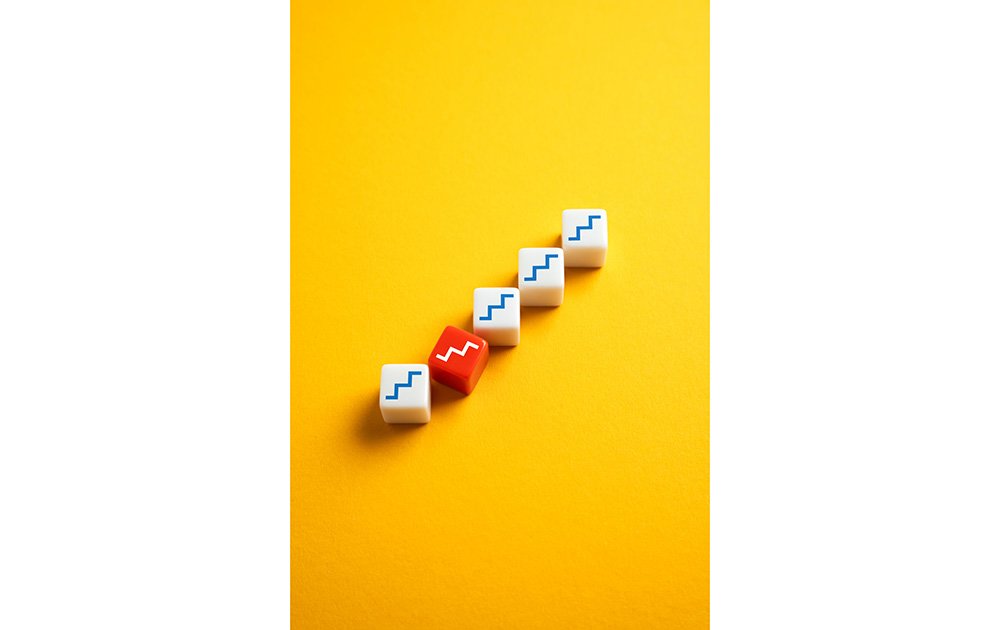
市場のリスクが一部の層に偏っている(写真:ilixe48/PIXTA)
誰の賃金を「守って」きたのか
労働組合は誰の賃金を守ってきたかという問いにシンプルに答えるとすれば、組合員の賃金を守ってきたといえます。ただ、その組合員は大企業の男性正社員が中心で、労働組合の組織率も年々低下してきたという問題があります。
労働組合が賃金に与える効果に関する研究は、効果があるとするものもあれば、ないとするものもあり、はっきりした決着がついていません。
私自身が行った研究では、個人の属性をコントロールした上で、労働組合のある企業の方が賃金が高いという結果が得られましたが、さらに企業規模をコントロールするとその効果が見えなくなりました。日本では労働組合のある企業が大企業に偏っていますが、組合企業の賃金が高いように見えたのは、実は大企業であるためだったということです。
ただし、同じ大企業であっても、労働組合のある企業とない企業で違いがあることもわかりました。それは、組合のある企業の方が、年功的な賃金カーブが維持されているということです。日本的な人事処遇が維持されてきたともいえます。
こうしたことから、労働組合が何を「守ってきたのか」といえば、日本的な処遇システムを守ってきたといえるのではないでしょうか。
年功的賃金の限界
日本の場合、労働組合のある企業とない企業の賃金差の大きな部分が、「勤続年数」から生まれています。具体的には、労働組合のある企業は勤続年数が長い人が多いことと、同時に企業が勤続に対してより高いリターンを支払っている、という二つの要因によってもたらされています。こうした賃金のあり方は、働く側からすれば、将来の見通しが立ちやすいというメリットがあります。
しかし、この仕組みには大きな問題もあります。それは、そうした処遇をすべての人が受けられるわけではないということで、日本の場合には性別と学歴で処遇が決まっていました。バブル崩壊後には、正規・非正規という形で同じ企業内でも異なる処遇制度を適用される人がいっそう可視化されました。経済が縮小し業績が低迷した際、企業はそのリスクを従来のメンバーシップの外側に押しやる形で、「非正規雇用」として外部化しようとしたのです。
「二重労働市場論」と日本
制度派経済学には「二重労働市場論」という議論があります(日本ではよく似た議論に「二重構造論」というのがあるのですが、本来は別の議論です)。
「二重労働市場論」は、先進国において資本主義が高度化し不確実性のリスクが高まると、それを引き受けるセグメントが必要となって、労働市場がまったく異質な二つ以上のセグメントに分かれるという理論です。先進国では第二次世界大戦後に労働組合の力が強くなり労働者の処遇が向上しましたが、皮肉にもそのことが一因となって、経済の不確実性が高まった際にその外側にリスクを引き受けるセグメントが出現したと言われています。
この理論が示唆するように、確かに非正規雇用の拡大は、どの先進国でも見られる現象といえます。しかしその内実は国によって異なります。例えば、ヨーロッパでは、パートタイム労働者でもフルタイム労働者と時給も福利厚生も同じという国があります。
一方で日本では、パートとフルタイムの間に賃金をはじめ、教育訓練やキャリアパス、雇用保障など、多岐にわたって大きな処遇格差が存在します。これは、不確実性のリスクが非正規雇用労働者に極端に偏っていることを意味します。
日本のもう一つの大きな特徴は、非正規雇用が女性に偏っていることです。不確実性のリスクを誰が担うのかは国によって違いがあり、「人種」が重要な国も「エスニシティ(移民)」が重要な国もありますが、日本では「性別」がその中心的な役割を担っています。
「二重労働市場論」への対策
「二重労働市場論」は、労働市場に異なる仕組みや制度が存在することを強調します。これは主流の経済学とは異なる考え方です。労働経済学の考え方を非常にシンプルに説明すれば、すべての人に同じルールが適用されると考えます。賃金は限界生産性に応じて決まるのであり、労働市場は生産性が高い人と低い人に分かれたとしても、生産性で賃金が決まるという原則は同じです。
しかし、現実はしばしばそのようにはなっていません。例えばスキルや生産性が同じであっても(こうした要因を測定するのは容易ではないのですが)、所属する企業や雇用形態の違いで大きな賃金格差が生じています。これは賃金が決して生産性だけで決まるのではなく、さまざまな仕組みや制度によって決まることを意味します。このように、企業や雇用形態など、労働市場のどこにいるかによって適用される制度が異なる点を重視するのが、「二重労働市場論」の主張です。
いまの日本では、正規と非正規でまったく異なる制度が適用され、その処遇は隔絶しています。そうした処遇差はこれまで、「正規と非正規では担っている仕事や、求められるスキル・責任が違うため当然」と受け止められてきました。しかし実際には、仕事内容やスキル、責任といった内容を客観的に測ることはとても難しく、十分な分析が行われないままに、処遇差が正当化されてきました。
問題は、こうした処遇格差が妥当なのか、ということです。埼玉大学の秃あや美准教授の研究では、職務評価を行うことで正規と非正規の仕事の重複を明らかにし、格差の妥当性を問い直しています。このように二つの制度を結び付ける仕組みが求められるように思います。
「雇用ポートフォリオ」との関係
日経連の「雇用ポートフォリオ」にひもづけていえば、「長期能力蓄積型」と「雇用柔軟型」とが、水平的な意味で異質なカテゴリーとしてではなく、正規雇用と非正規雇用という形で、垂直的に序列があるカテゴリーとして位置づけられ、それが性別と強く結び付いてしまったところに問題があったといえます。
さらにいえば、「高度専門能力活用型」が育たなかったことも課題です。とりわけ問題なのは、専門的なスキルが日本の労働市場の中で正当に評価されていないことです。本来であれば「高度専門人材」として位置づけられるべき人々も、現状では「雇用柔軟型」として処遇されてしまっています。特に近年は公務職場においてその問題が顕在化しています。
同じような仕事をしているにもかかわらず、正規と非正規の間に大きな処遇格差が存在する現状は、社会の公正さが大きく損なわれ、社会を停滞させています。非正規雇用が広がった国では、公的セクターでサービスの質が低下する問題が深刻化し、処遇格差を是正しようとする動きが広がっています。日本でも同様の取り組みが求められると思います。
労働組合への期待
日本の労働組合は、社会において相対的に強い立場にある正社員を中心に組織されています。ただ労働組合とは本来、社会的に弱い立場に置かれた人たちの権利を守る存在です。中小企業や非正規雇用との間に格差が存在し、さらにはフリーランスといった働き方が広がっています。労働組合が活動の幅を広げ、働く人をどのように守っていけるかが問われていると思います。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

