職場のダイバーシティー推進
一人ひとりが働きやすく能力の生かせる社会へ雇用形態間格差と
働き方のジェンダー化
是正のために職務評価の導入を
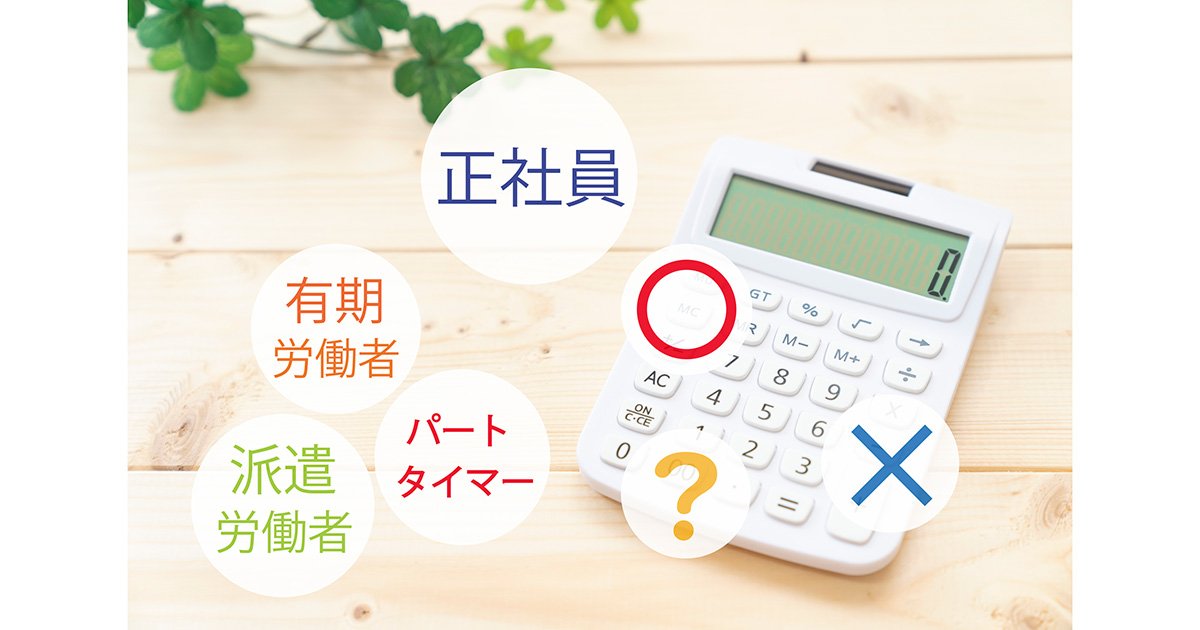

解消されない格差の背景
──雇用形態間の格差が解消されないのはなぜでしょうか?
日本で雇用形態間格差が解消されない背景には、働き方のジェンダー化があります。働き方のジェンダー化とは、本来はジェンダーに結び付いていない働き方が特定の性別に結び付き、偏りを生じさせていることです。例えば、パートタイム労働は、これまで女性と結び付けられてきました。
日本における働き方のジェンダー化の一番の問題は、正社員の働き方があまりにも男性化し過ぎていることです。つまり、正社員の働き方が、男性が働き、女性が家事責任を負うという性別役割分業のあり方に合わせ過ぎているということです。そのため、そこに適合できない人は正社員からこぼれ落ち、非正規雇用にならざるを得ません。処遇のあり方も、性別役割分業に基づき、男性は家族を養うことができる処遇、女性は家計補助的な処遇とされてきました。ケアの責任を負うか、長時間労働や転勤ができるかという性別役割分業に基づくジェンダー化によって雇用形態が区別され、処遇格差が固定化されてきました。
──そうした格差を是正するために何が必要でしょうか。
雇用形態間の格差がこのように「働き方」の違いに基づいていると、その格差が合理的かどうかが判断しづらくなってしまいます。つまり、同じ仕事に対して同じ処遇なのかを比べようとしても、配置転換のような人材活用の仕組みを基準していると、比較を難しくしてしまいます。現在は、転勤や長時間労働のような見えやすい働き方の違いによって格差を納得させようとしていますが、それでは雇用形態間格差が本当に合理的なのかの議論が深まりません。例えば、正社員と同じ仕事をしているパートタイムの店長であっても、通勤の範囲が違うというだけで大きな処遇格差をつけられることがあります。こうした賃金格差は果たして合理的なのか。こうしたことを議論するためのものさしが必要です。
共通のものさしの必要性
──どのようなものさしがあれば雇用形態間の格差を合理的に説明できるようになるでしょうか。
そのための社会的な物差しが、職務評価です。職務評価とは、職場の仕事を分析し、その職務に点数を付けることで、仕事の価値や分布などを客観的に表示するための仕組みです。職務評価を行うことで正社員と非正規雇用という雇用形態の違いに関係なく比較が可能になります。
これまで労働分野の研究では、パートタイム労働は外部労働市場の労働力として位置づけられてきました。内部労働市場の正社員は「人基準」で評価される一方、外部労働市場のパートタイム労働者は「職務基準」で評価されるため、異なる労働市場に属するという説明です。
しかし、実際の職場で職務評価を行ってみると、内部労働市場にいる正社員も、職務の難易度が処遇にかなりの割合で反映されているということがわかりました。別々の労働市場に属するはずの労働者であっても職務評価を使えば共通のものさしで比較できるようになります。
私はこれまでいくつかの職場で職務評価を実際に行ってきました。その結果、高い役職に就いている人は職務評価点が高く、職務評価点の比率どおりに賃金が支払われていることや、パートタイム労働者の賃金は、職務内容に見合ったものではないことなどがわかりました。職務評価というものさしを使えば、制度をまたいだ比較が可能になります。
──職務評価を用いるメリットは?
職務評価は、非正規雇用の低処遇を是正するだけではなく、正社員の働き方を変えることにもつながります。
日本の正社員は、「いつでも何でもどこでも」といった拘束的な働き方と引き換えに、雇用と賃金の安定という保護を享受してきました。しかし、このように「残業できる」「転勤できる」ことなどを理由に格差を正当化すると、非正規雇用の低処遇は追認される一方、正社員はいつまでたってもそこから抜け出せません。
職務評価を使い職務をベースに処遇を決めると会社はそれまでのような強い人事権を行使できなくなります。その結果、無限定な正社員の働き方を変えることにもつながります。正社員の働き方を変えるためにも職務評価の活用は重要です。
また、これまでの「同一労働同一賃金」を巡る議論でも、現在の配置転換などの人材活用の仕組みを重視したあり方では、基本給の問題に踏み込みませんでした。「同一労働同一賃金」を進めるためにも職務評価が必要です。
連帯のための道具
──職務評価を進めるために何が必要でしょうか?
正社員であっても、これまでのような無限定の働き方をしたくない人は増えています。転勤や配置転換が離職の理由になり得ます。その中で企業としても公平な処遇のために職務評価を行う必要性が高まると思います。
ただし、職務評価は経営者だけが行うと公平なものにならない可能性があります。職務評価を経営者だけに任せると経営者の都合の良いように職務の点数を設定されてしまいます。職務をどのように評価するのか、労働者側の意見を反映させることが不可欠です。その意味で、働く側が主体的にもっと関与する必要があります。
──ダイバーシティーの推進のためにも職務評価は重要になるでしょうか。
働き方がジェンダー化したままでは、男性的な働き方ができる人しか評価されず、職場の同質性が高まり、多様な人材の能力を生かすことにつながりません。ダイバーシティー経営を追求し、多様な人材が活躍できる基盤を整える上で職務の掘り下げは不可欠だと思います。
ジェンダー化された働き方は、ケアの負担のない男性的な働き方を標準にしています。このようにケアを度外視した標準的な労働者像は、ケアの負担を会社の外部に押し付けることで社会全体に悪影響を及ぼしています。
こうした働き方を変えるためにも職務評価が重要になっています。職務評価に対する社会的な合意を形成していかなければ議論は前に進みません。職務評価は働き方を変えるための「武器」の一つであり、雇用形態で分断された労働者が連帯するための道具の一つだと考えています。労働組合の皆さんの現場からの実践に期待しています。
![情報労連[情報産業労働組合連合会]](/common/images/logo_ictj.png)

